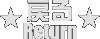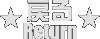|
「リオネちゃんが起きないって……どういうことなんですか!?」
植村の驚いた声に、市長はかぶりを振った。
「わかりません。最初は、疲れたのだろうと思っていたのですが……、いつまでも目覚めないのです」
「たしか、以前にもそんなことが……」
「ええ。あのときはリオネの心がネガティヴパワーにとらわれてしまっていた。でも今度は……あのマスティマを倒した直後なわけですし、どうもそういうことではないように思います。そして、今朝からさらに“異変”が」
「異変とは?」
マルパスが訊いた。
「見たほうが早いでしょう」
柊市長邸は、マスティマ戦において全壊の憂き目を見た。
よって市長とリオネは市内のホテルに移動している。
市長と植村、そしてマルパスはエレベーターに乗り込んだ。
「ミダスたちは何も語ってくれません。3将軍は、傍にはいるのですが。かれらは、リオネが、剣を加護に変えて私たちを助けてくれたことで、われわれに助力をもたらすことをやめてしまったようなのです」
市長はため息とともに言った。
「神々は銀幕市には介入しないことになっていたのですものね。リオネちゃんは――結果として、またしても神々のルールを破ってしまったことになる。……まさか、それで……!?」
「3将軍や、オネイロスがほのめかし、リオネも時々口にしていましたよね。リオネはいつか『罰』を受ける。あの選択の時に、タナトスの剣による罰の執行は選ばれなかった。しかしリオネが『罰』を受けなくてはならないことに変わりはなく、まして、その罪が増してしまったのだとしたら……」
話しているうちに、部屋についた。
市長がカードキーでドアを開け、2人を中へ案内した。
「!?」
植村とマルパスが息を呑む。
ベッドのうえで、リオネが寝息を立てている。
だがその姿は、うっすらとしか見えなかった。彼女の周囲を、虹色の雲のような、ふわふわとしたものが覆い、彼女を包みこんでいるのである。
3将軍は彫像のように部屋に立ち、その様子を見守っているかのようだった。
「……朝よりも、層が厚く、輝きが増している」
市長が言った。
「これは……リオネちゃんの『罰』なのですか……」
植村は、返答を期待せずにミダスに問いかけた。
だが意外にも、ミダスはそれに頷いたのだ。
『左様。ついにその時が来た』
「まるで」
マルパスが言った。
「繭のようだ」
3人は対応を協議したものの、見守る以上のことができるとは思われなかった。
そして、どれくらいの時が過ぎただろう。
「あ――」
誰かが声をあげた。
虹色の繭は、そのときまでにリオネの姿が完全に見えなくなるまでになっていたのだが、その輝きが、急速に強まり、部屋中を虹色の光で染め始めたのである。
「こ、これは!」
「おお……」
そして、光が、弾けた。
眩い虹のきらめきが飛び散り――その中に、シルエットが浮かび上がる。
光は、空気に溶けるように消えていった。
そしてそこに、ひとりの女性が、立っている。
流れる銀の髪。不思議な色の瞳。その面影は、たしかに。
「……まさか……リオネ……」
「ええ」
彼女は頷いた。
「私はリオネです」
しかしその姿は、まぎれもなく、成人した女性のそれであったのだ。
★ ★ ★
その報せは銀幕市中を駆けめぐり、驚きをもって迎えられた。
リオネは皆に話さねばならないことがあると言って、植村に広報を頼み、銀幕広場へと赴いた。
そして、集まった大勢の人々を前に、大人になったリオネは、語るのだった。
「みてのとおり、私はもう子どもではありません。私の『罰』が成就されたのです」
『神の子は数千年を幼きまま生きる』
黄金のミダスが補足するように言った。
「無邪気で気楽な子ども時代を早々に終えなくてはならない――、これは神々にとっては最大の『罰』だというわけだ」
イカロスが続ける。
「そしてこの『罰』は、この一件のはじまりからおわりまでを『見る』ことで、リオネ本人が、心の底からその『罰』を甘受する必要性を理解したとき、達せられるものだった。オリンポスがそう決めたからな」
最後はタロスが締める。
「私はこの『罰』により、大人になり、正式に、女神のひとりとしてオリンポスの神々の列に加わり、その責務の一端を担うことになります。具体的には、父オネイロスの力の一部を継承します。ですから、みなさん……。私は、神の世界へ帰らなくてはなりません」
聴衆がざわめいた。
3年前、この地に魔法をもたらしたちいさな神の子の、それは別れの挨拶だったのだ。
「魔法は? 銀幕市の、魔法は……!?」
耐えかねた誰かが聞いた。
そうだ。誰もがそのことを知りたい。
リオネは頷いた。
そのおもてに、いいようもない哀しみをたたえて。
「あの戦いの日、私は自らの魔法に『終わり』を命じました。魔法を完全に制御できるようになった今、あのときの命がゆるやかに効果を現し始めているのです。……私は、この現状を見守るだけに留めねばなりません」
しん、と広場は静まり返った。
リオネは、虹色の瞳で、その場にいる人ひとりひとりの顔を、確かめようとしているかのようだった。
「……私の『罰』。私は、はじめからおわりまでを見るまでは、ここにいます。悲しむことはもちろん、憤ることも自然なことです。私を憎むことも、私はすべてを見届け、引き受けます」
群衆のあちこちから、諦めのため息や、押し殺したすすり泣きが聞こえてきた。
「……魔法の終焉は、ミダスの見立てによると6月13日。あの時もしもタナトスの剣によって私が罰せられていたら、そのような時間は与えられなかったでしょう。皆さんが、選択によって手に入れた時間なのです。……どうか、最後のひとときを穏やかに過ごされることを、私は望みます」
|