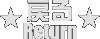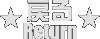|
<ノベル>
「ほうほうほう、これが『銀幕市カレー』とやらか!」
チャンドラ王子の目が輝く。
そこは綺羅星ビバリーヒルズの一画にあった空き屋敷を王子が買い取り、またたく間にインド風に改装させた「チャンドラ宮殿」――さながらタージマハルが銀幕市に移築されたかのような、ぱっと見、インド映画のムービーハザードだろ!というような感じの、彼の居宅であった。
ちょっとしたイベントホールくらいはあるこの壮麗な宮殿の奥に、SAYURIはほぼ軟禁状態で住むことを余儀なくされていた。幾人もの、インドから連れてこられた侍女たちにかしづかれ、物理的な不自由はなかろうが、内心、かなり苛ついていることは、彼女をよく知るものならその表情でわかっただろう。
それでも大女優は、一見はあくまで優雅に、豪奢なサリーを着こなして、王子とともにテーブルについた。
長いテーブルの末席には、緊張した面持ちの植村。
そして、このカレーづくりに尽力した簪、ルークレイル・ブラック、リゲイル・ジブリール、セバスチャン・スワンボートの4名。本田流星は、あいにくホテルの仕事で本日は欠席である。
そして、『銀幕市カレー』が運ばれてきた。
王子の手のなかに3本のマイ・スプーンがあった。金・銀・銅のこのスプーンは、インド神話の3大神、ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァを象徴するらしいがそんなことはどうでもよい。王子はそのうちのひとつで、おもむろにカレーをすくい、口に運んだのである。
「ほほう」
このカレー、なにせ、銀幕ベイサイドホテルの総料理長が手がけた品である。世界的な美食家である王子の舌をも満足させる、それは美味であった。
「なかなか深い味わいだ。これは……見たことのない野菜だな」
「日本の山に自生するヤマタネツケバナという野草です。日本でも、大変、珍しいものです」
植村がギャルソンのごとくに解説を入れる。
「しかも色とりどりの……美しいではないか。良い風味だな」
山菜は王子の口に合ったようだ。
植村のおもてに緊張の色がさす。そうだ――それは神獣の森で摘まれた、神秘の力をもつ山菜。はたしてこれが、吉と出るとか凶とでるか――!
「……!?」
極彩色の花吹雪!
打ち鳴らされる打楽器のリズム。幾重にも重なるコーラス。
風が、花びらとともに、彼のまとうきらびやかな布をはためかせた。
「何故だ。わたしの花嫁となりさえすれば、七つの大陸と九つの海はすべて、そなたのものだというのに」
女の、黒曜石のような瞳が、そんな彼に、憐みのような眼差しを返すのだった。
「……恐れながら申し上げますわ、王よ」
SAYURIは応えた。
無作為に映画の幻覚を見るのがこのカレーの効能。
大女優は、チャンドラの見るのが、インド・アメリカ合作のファンタジー大作、『聖王の剣』だと見抜いたようだ。
英雄にして暴君たる征服王を、チャンドラが演じた。
彼に求婚されながらそれを退ける亡国の姫役は、SAYURIではなかったけれど、驚くべきことにそのセリフは一言一句、映画のスクリプト通りだった。
「目に見え、手に触れられるものを持てば持つほど、目には見えず、手に触れられないものは遠ざかっていくものですわ」
「……っ!」
チャンドラは、額の脂汗をぬぐい、頭を振った。
「なんだこれは! こ、これが銀幕市カレーだと! 余を――魔術で惑わそうという魂胆かっ!」
「チャンドラ王子」
王子の剣幕に、植村が、しまった、と絶望的な表情を浮かべたのに対して、SAYURIはいささかも動揺することなく、彼に語りかける。
「神獣の森ではなくても……この銀幕市は山に囲まれ、もともと山菜の実りはゆたかな土地。わたし、山菜は好きよ。山菜って、すこし苦いものが多いでしょう。それがね……生命の味だ、という気がするの。人生って……」
SAYURIはほほ笑んだ。
それは寂寥を含んでいるようでいて――ぞっとするほどに艶然としたうつくしさを持っていた。
「人生って、苦いものでしょう?」
「…………」
食卓に流れる沈黙。
そして。
誰かが笑い出した。
誰あろう……チャンドラ王子その人だった。
「余にそれを……教えようと、か。SAYURI、そなたは……」
かぶりを振った。
「まだ余には御しきれぬと……余ごときには御されぬと云いたいのだな」
くすり、と女優は笑う。
「……よかろう。ならば、いつか……余がそなたにふさわしい男になったときに、あらためて求婚しようではないか」
「ええ。お待ちしておりますわ。王子」
「え!」
この言葉はちょっと意外だったので、植村が声をあげた。
「王子。このカレーを作って下さった方に、ご褒美をいただけないかしら」
「おお、そうであった。みな、大義であった。礼を言う」
王子は4人の市民に向かって言った。
「みなには褒美をとらせよう」
そして、王子が手を叩く。
ルークレイルはほくそ笑んだ。これで苦労の甲斐があった。インドのマハラジャの息子で、大富豪であるという王子のこと。これはさぞ高価なお宝を頂戴できるに違いない。
眼鏡の奥で、期待に輝くルークレイルの青い瞳は、しかし、それを見て見開かれた。
「な、なに……?」
「これはまた面妖な」
簪が、声をあげた。幕末からせいぜい明治のころの日本に似た世界からやってきた彼が、それを知っていただろうか。知っていたにせよ、相当、珍しいものであったに違いない。それがいま、のしのしと、かれらの前に連れてこられる。
「素敵!」
リゲイルが、実に素直に喜びの声をあげた。
それはさながら、子猫か子犬を差し出された少女の反応だ。
「いや、待てよ、おい」
しかし、常識人たる(?)セバスチャンは、戸惑わずにおれなかった。
そこに居並ぶのは、猫や犬ではない。
……ゾウなのだ。
ゾウとしては小さいほうで……子どもなのだろう。
きらびやかなインド風の飾りを身につけた子ゾウが4頭。ひとりに1頭ずつということだろうが……、それが、王子からカレー作成者たちへの贈り物なのだった。
「……そうそう、植村さん。他にも試作品のカレーがあるのですって? せっかくだから王子に味わっていただいたら?」
SAYURIが、どこか悪魔的な笑みを植村に向けた。
「え? あ、あの……ほかの候補作ですか? それは構いませんが……いやでもですね……」
植村は焦ったが、大女優の意向に逆らうことなどできず、ほどなく9種のカレーが運ばれてくる。
「お、ナンを添えたものがあるな。和食や洋食もいいが、続くとナンが恋しくなるものだな。これはグリーンカレーか、どれ……」
「あ、王子、それは」
よりによって、もっとも危険度の高いカレーが、チャンドラ王子がまっさきにスプーンを近づけたものだった。
その後の出来事については、銀幕ジャーナルにインド政府から圧力がかかって削除されたという噂である。ひとつ言えることは……、SAYURIは、王子にその罪の代価は十分に支払わせたのだということだ。
|