ドラグレット戦争
![]()
![]()
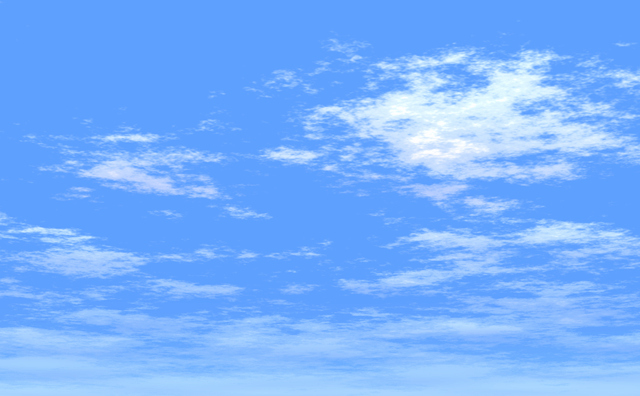
![]()
 オープニング
オープニング
太鼓の音が樹海に響く。
鳥たちがぎゃあぎゃあと鳴きながら飛び立ってゆく。
木陰の動物たちもどこか落ち着かない。
「森が慄いている」
ドラグレットのまじない師たちが厳かに告げるなか、戦士たるドラグレットたちは武器を携え、その時に備えた。
「勇敢なる戦士たち」
樹海の奥深く、ひっそりと隠れるように存在していたドラグレット族の集落は、その日、熱く沸き立っていた。
《翡翠の姫》エメルタが、戦士へと呼びかける。
「悪しき魂が、森を侵すのを許してはなりません。この地はわれわれの聖地にして、この大地そのものの源につながる場所なのですから。……客人エドマンドの友人たちが、このたびの戦に力を貸してくれます。かつて、エドマンドがそう約束してくれたとおりに」
ドラグレットたちの瞳が、ロストナンバーたちに向けられた。
館長の足取りを追って、前人未到の樹海を旅してきたヴォロス特命派遣隊、そしてその援軍要請にともない、急ぎターミナルから駆けつけたもの。かれらは今、ヴォロスの古き種族ドラグレットとともに、かれらの領域へ侵略を企てる軍と、斬り結ぼうとしているのだ。
太古の時代、ヴォロスを支配したとされるドラゴンの末裔、それがドラグレットだ。かれらはワイバーンなる小型の飛竜を駆り、空を征く勇猛な戦士だった。樹海を開拓し、おのれの領土拡張を目指す人間の国、ザムド公国は、竜刻使いの一団の結び、魔力で空に浮く船を手に入れた。その力をもってすれば、ドラグレットをも退けられると考えているようだ。
なるほど、いかにワイバーンに騎乗し、空中戦も挑めるとはいえ、ドラグレットの原始的な武器だけでは心許なかっただろう。だが今は、ロストナンバーたちがいる。
戦いは、ドラグレット精鋭による小隊が、飛空船を襲撃するという形で行われる。
ロストナンバーも小班に分かれ、ドラグレットの部隊に加わることになる。
戦意を高揚させる打楽器のリズム。燃え盛るかがり火。
やがて、見張りのドラグレットが、空の彼方にその影をみとめた。
ザムド公国の飛空船が、再び侵攻を挑んできたのだ。
「よし、いくぞ!」
荒々しい雄叫びとともに、竜の末裔は、愛騎とともに空へ。
これこそのちに、ヴォロス辺境の歴史書にひそやかに記された「ドラグレット戦争」の始まりであった。
 ノベル
ノベル
騒然とした空気。
しかし、どこかに高揚感も。ドラグレットたちにとって、その必要があれば戦いに身を投じることは当然のことであるようだった。
藤枝竜が火打石を鳴らして、戦士たちを送り出す。
思わず石だけでなく、吐息にも炎がまじる。
「私は竜刻使いじゃないですよ。これは体質です」
次々と、飛び立っていくワイバーンたちを見送った。
「みなさん、ご無事で……!」
やがて戦場になるであろう空の彼方は、今はまだ青く澄み切っている。
(私にもっと力があれば――)
たとえば、そう……本物のドラゴンほどの力があれば、ここで皆の帰りを待つだけには甘んじない。あの空を駆け、戦うこともできるのに。
「さて、と」
ぐっ、と拳を握りこみ、竜は集落に残るものたちを振り返った。
「支度をしましょう。祝勝会の」
「もう始めてる」
椙 安治が両手いっぱいの食材を持って、竜の前を横切っていく。
「ただ待ってても暇だろォ?」
「あ、手伝います!」
「邪魔はするなよ」
「火を起こすのは得意ですから!」
「へへっ」
安治は片頬をゆるめて応えた。
宴の夜に、ドラグレットたちの料理は覚えた。実に素朴な、素材の無駄のない食生活をかれらは送っている。
「凝って見せても受けそうにねぇな。質より量ってな連中ばかりだからな」
言いながら、素早い手つきで下ごしらえに入る。
「けど、ま……、せいぜい、うまいもんでも作ってやるかね」
「包帯はここでいい?」
「ああ。数は足りるだろうか」
「これだけあれば大丈夫だと思うよ」
晴秋 冬夏と、高城 遊里が、救護用品の準備をしている。
ドラグレットの薬師たちも、不思議な匂いのする薬を、草をすりつぶしたり、乾燥させた木ノ実を煎じたりして作っているようだった。そして精霊へ祈りを捧げる祈祷師たち。壱番世界でも前近代の社会がそうであったように、ここでは医術と魔術の境目がない。
「ザムド公は」
遊里は、傍にいたドラグレットに話しかけた。
「なぜこの地を狙うんだろうか。あの船だって、用意するのは簡単なことじゃない。向こうも相当の犠牲を払うことになると思うが」
「それはここが聖地だからさ」
薬師の見習いだという歳若いドラグレットは答えた。
「この世はかつて、ドラゴンによって創られ、治められていた。この世のすべてはドラゴンのものだった。今はもうドラゴンは亡く、その叡智のごく一部だけをドラグレットが継承している。ドラゴンの力があれば、世界を意のままにできると、愚かな人間は考えるのだろう。そしてその力を、この地が隠していると。愚かなことだ。ドラゴンの力を、御することなどできはしないのに」
「竜刻――ということか。ここにも……ドラグレットも竜刻を?」
「むろん。ただ、われらは、竜刻使いのようにむやみにそれを振りかざしたりはしない。竜刻は聖なるものだから、聖地に静かに眠っているべきだ」
ふと気づくと、晴秋 冬夏は集落の子どもらとともいる。
かれらの不安をまぎらわせるように、明るい声で遊びに誘う。冬夏が教える壱番世界の遊びを子らはすぐに教えて、戦時下とも思われぬ笑い声が、集落に響きはじめるのだった。
*
ターミナルから馳せ参じた援軍と、派遣隊の面々は、ドラグレットたちとともにワイバーンの背に乗り、あるいはそれぞれの方法で空を翔けていた。
目指すは飛空船。
膨大な魔力により宙に浮かぶ船だ。
「ゴメン……重イ……カナ」
幽太郎・AHI-MD/01Pの、メカボディは、ワイバーンにはいささか重い荷物だったろうか。それでも飛び続けてくれる騎乗竜に感謝の念を抱きながら、幽太郎はなすべきことへと集中する。
センサーの出力を最大に。どんな情報も逃さぬように広い集める。そしてそれをすみやかに仲間たちに伝えるのが彼の役目だ。
『メインシステム……偵察モード、起動完了……。……情報分析処理……開始……』
迎撃目標と、それへ向かう味方軍の位置関係を把握。
立体的に、関連する情報が紐付けされてゆく。
『今ノ相対速度ノママナラ、アト8分デ、先頭ガ交戦圏内ニ入ルヨ』
幽太郎の分析結果はトラベラーズノートなどを通じてロストナンバーたちに広まり、そして、ドラグレットたちにも伝えられていった。
「うおおおお現在っ私はぁぁぁぁ!! わいっ、ワイバーンの背中にてぇぇぇ!」
「うるさい! 誰に話してるんだ!」
本郷 幸吉郎の実況を、彼が乗るワイバーンを御するドラグレットが一喝する。
「い、いや、この状況を伝えないと……って、うおおおおぁぁぁあああー!!」
「あっ!?」
落ちた。
猛スピードで飛ぶワイバーンから放り出された幸吉郎の身体が宙に舞う。
視界が回転し、天地が逆転する。そして――
ぴん、と張ったロープがかろうじて彼を支えた。文字通りの命綱。命拾いだ。
「おおおおお、間一髪であります! さて、私たちは迫り来るザムド公国軍の船へ向けて……」
「何やってんだアイツ」
ドラグレットが呆れて見下ろす。
飛び続けるワイバーンに綱で吊り下げられたような格好だ。
「先ほどの連絡では、あと10分弱で交戦圏内に――ぃいいい!?」
ひゅん、となにかが頬をかすめた。
下だ。下方の樹海からなにかが――いや、矢が射かけられている。
「下です! 下にも敵があああああ!」
幸吉郎の大声が響き渡った。
「なんだと!?」
視界の中を、数匹のワイバーンが旋回する。
その一匹の背には、ドラグレットとともにキース・サバインの姿があった。
「森の中にも……いっぱいいる。百……いや、もっとだぁ」
「まずいな。村に知らせないと」
ドラグレットが渋い表情をつくる。船とは別に地上部隊がいたとは。
「俺の仲間がいるから」
キースがノートを使って事の次第を報告する。
『……コチラデモ確認シタヨ。地上ニ多数ノ生体反応。移動速度ハ遅イケド、僕タチガ船ニ向カッタラ、集落マデガラ空キニナッチャウ』
むろん、それを許すロストナンバーではない。
情報はただちに集落へ伝えられ、地上部隊を迎え撃つ戦士たちが動き出したのは言うまでもなかった。
「くそっ、乗り心地が悪いな……。手綱を貸せ、私が操縦する」
アインスがそんなことを言い出した。
乗り手のドラグレットは驚いてもちろん拒んだが、アインスは、
「キミよりも私の方が操縦が上手いに決まっているだろう、私は天才だからな。つべこべ言わず早く寄越せ」
と手綱を奪いとってしまった。
「よし!」
ぐい、と引けば、高く舞い上がる。
湿り気をおびた樹海の風がアインスの頬をなでた。
要領は乗馬と同じ、とあたりをつけた。手綱をゆるめ、足で合図してやれば、急降下だ。風を滑るようにワイバーンが降りてゆく。その加速のまま、今度は進路をまっすぐに。目指すは敵の飛空船。
大勢のワイバーンが、背にドラグレットとロストナンバーを乗せ、そこを目指していた。
「全軍、突撃いィィィィィィィィィィ!!!!!」
首狩り大将オウガンの胴間声が響き渡る。
ワイバーンの部隊は数名ずつの小隊に分かれ、飛空船を取り囲むように散開する。それぞれが船を牽制し、その1隊が内部に飛び込むという作戦だ。
その直前――
「おい、そこの小僧!」
オウガンが、すこし離れて着いて来るモビール・オケアノスに声を掛ける。
「無理はするな」
「……! でも――」
「気ばかり先んじても意味がない。アドンの小童と同じだ。おまえは……他人のような気がせんから忠告してやるんだ。アドンなんかよりずっと同族みたいだ。本当にドラグレットじゃないのか?」
「……」
「この下にも――いるな。おまえはそっちを頼む。適当に何人か連れて、さあ行け」
モビールは頷いた。
オウガンは、ロストナンバーを含めた幾人かと船のほうへ。オウガンに随行する、派遣隊の仲間が、こちらは任せろとばかりに、目だけで意思をかわす。
モビールは、眼下の樹海をまっしぐらに目指した。
幅広の両手剣を握りしめる。
ドラグレットが、自身と似たような姿の種族と知って、不思議なめぐり合わせのようなものを感じた。
(ここで、ぼくは)
裂帛の気合とともに、樹冠を突き破る。
驚く敵兵に斬りかかった。
(一人前の戦士に……!)
飛空船へ接近する部隊を、ロストナンバーたちが援護する。
あるものは遠距離攻撃で。
あるものは、飛空船からあらわれた敵の空中戦力と斬り結んで。
「森と、そこに暮らす者に仇なすのはねー」
やっぱりいけないことだよ、と青燐。
事前にドラグレットから分けてもらっていたのは樹海の植物の種だった。それは瞬く間に槍のような形状に育ち、青燐の手から放たれるや、まっすぐに飛んでゆく。生きた植物の槍だ。
敵軍は、グリフォンなどの飛行生物も用意していたらしい。それらに騎乗した敵の騎士たちとドラグレット軍との戦いもあちこちで始まっていた。
しかし敵の騎士たちはドラグレットと違って空中戦には慣れていない。なにより、ワイバーンのほうが、空飛ぶ生き物として、その速度が上回っていた。
「ふん――」
すれちがいざま、檜扇をふるえば、黒藤 虚月の鋼糸が敵兵を斬り裂く。
「……まだ墜ちぬか、しぶといのぅ」
血まみれになってなお、グリフォンを旋回させ、虚月に追いすがろうとする敵へ、彼女は日頃はあまり使わない術を行使する。たちまち悪夢にとらわれ、正体をなくした騎士が落下する。
――と、そのときだ、太陽が陰った、かと思えば上方から襲来する別の敵!
「!」
「させないわ」
閃く鋼色。トリニティ・ジェイドのトラベルギアが、五本の爪となって、敵兵の剣を受け止めた。
ドラグレットが操るワイバーンの背に立ち上がり、そのまま相手を押し返したかと思えば、甲冑の隙間を正確に突いて、刺す。
うめき声とともに崩れる敵をよそに、虚月を振り返った。
「すまぬ。空での戦いは得手ではない」
「あら、私は好きよ。高いところはね」
目もくらむほどの高空でも、トリニティは動じる様子がなかった。
肩にオウルフォームのセクタン、タイムを乗せて、相沢 優も援護に勤しむ。
「……っと! 危ない!」
トラベルギアの剣の能力で防御壁を展開し、射かけられた矢を弾いた。
飛空船には銃眼のような小窓がいくつも開いていて、近づきすぎるとそこから攻撃を受けてしまうようだ。だが防御壁に守られているならば。
「もっと近づける?」
「できるが……さっきのは魔法か?」
「そんなところかな」
「よし」
ドラグレットはひとつ頷き、そしてワイバーンが船の壁ぎりぎりと飛ぶ。
目に見えぬ壁に守られているとはいえ、ドラグレットにしてみればそれが本当に信用できるのかと考えてもいいはずだった。だが彼らは信じている。ロストナンバーが約束を守ってくれることを、あっけないほどの率直さで信じているのだ。
それに応えんとばかりに、優は剣を振るい、射撃窓からのぞいた敵の弓の先をへし折っていくのだった。
オルグ・ラルヴァローグは、仲間の能力で授かった羽により、空中にただずむようにしていた。
彼の双眸が見据えるのは、その「時」である。
すなわち、飛空船が、火を吐く瞬間だ。
それもまた竜刻の力なのか、別の機構が組み込まれているのかは知らないが、それが燃え盛る火炎の弾丸を撃ち出すことはすでに知れている。
果たして、ごう、と音を立てて火の玉が撃ち出されるやいなや、オルグは動いていた。
「伊達じゃないぜ――炎の金狼の二つ名はな!」
さながらその残像は、金色の流星だ。
その軌跡が、火炎弾と交錯すれば、樹海の空に炎の華が大輪に咲いた。
「そこか……!」
彼が狙っていたのは、火炎弾の発射口、あるいは砲手だった。
どうやらいくつかあるようだが、今しがた発射した箇所はわかる。金の狼人はまっすぐに、そこへと飛んだ。近づけば、船の外壁に穿たれた凹部の中に砲台があり砲手らしき連中が、右往左往している。オルグの接近と意図に気づいたのだ。
そして、そこに再び炎が充填されつつある。
「目を閉じろォ!」
誰かの声――しかしそれが仲間だとなぜだかわかる。オルグにとって、真実の声は常に澄み切っているからだ。
瞬間、閃光が炸裂した。
オルグが目を開けると、砲手たちが目を覆っている。
そこへ斬りかかった。
さらに、輝く小さな光の粒が、機関銃のように降り注いで、敵を打ち倒していった。
「いぇーーい、命中ーーーー!」
モック・Q・エレイヴだ。自身の身体の一部を撃ち出して攻撃した。
オルグが振り仰ぐと、閃光手榴弾で援護してくれた坂上 健が、ワイバーンで旋空していく。手をあげれば、向こうも応えた。
「やっぱり旅の終わりにはお土産が必須だよね♪ 森にはなんもないみたいだし、ここからいただくしかないでしょー?」
モックがそう言って、砲手たちのポケットをまさぐっている。
ほどほどにしろよ、と言い残し、オルグはまた空へと飛び立った。
「右斜め下だ。回りこめるかっ?」
「もちろん」
戦ううちに、坂上 健と、彼を乗せてくれているドラグレットの騎手の呼吸はすっかり一致していた。
飛行動物で天翔ける敵の騎士を牽制し、船からの射撃をかわし、突入部隊の成功までの時間を稼ぐ。
「目がいいな」
「え?」
「まるでたくさんの目があるようだ」
「ああ――」
空に放っているセクタンの、ミネルヴァの眼に助けられているのだ。だから戦場を広く見渡し、動くことができた。
「コックピットの位置がわかるといいんだが……」
「なんだって?」
「船の操舵室。……ん、あれは……!」
「ああっ」
すでに、船の内部でも、激しい戦闘が行われているようだった。
外壁が内側から壊れるところを、健は目にする。そこから、壁材とともに人の身体らしきものがバラバラこぼれおちる。敵兵だけでなく、その中にはドラグレットらしきシルエットも見えた。
「畜生」
騎手が唸った。
ごくり、と健の喉が鳴る。実にあっけなく、ゴミくずのように落下していくあれも、人間だった。ザムド公国の騎士や傭兵は、たしかに悪だと言っていい。しかしかれらにもまた人生があったのであって。
「戦争だよ、確かにな!」
健は声を張り上げた。
そして騎手の背中に向かって言うのだ。
「なあ……ザムド公は悪だ。でも、だから! この戦いが終わったら、その後は……人間もこの地に生きる仲間だ。今は無理でも、何世代か後には手を取り合えるかもしれないだろう?! お願いだ、その希望まで摘まないでくれ!」
「異邦の旅人よ」
騎手は振り返らずに応えた。
「ドラグレットは大いなるドラゴンよりこの大地をたくされた種族だ。憎しみだけにとらわれることはない。そこは見くびらないでもらおう。だが……おまえたちは優しいな。旅の途中だというのに」
そのとき、陸 抗は飛空船の内部にいた。
能力で浮くことができるからワイバーンは必要ないし、この戦場の騒乱の中では、彼のサイズはほぼ見過ごされる。だから難なく、突入部隊が開けた穴から、船の内部に侵入し、あちこちで船の中のものを壊したり、駆けまわる敵兵を能力で打ち倒したりして、船内を混乱させていたのだ。
「ん」
空気の中にもうもうと煙が混じり始めていた。
船が燃えているのだろうか――いや、これはどちらかと言えば煙幕か何かのようだ。突入部隊が発煙筒でも使ったのかもしれなかった。
「……」
窓枠へと飛び移る。景色が動いていた。
どうやら操舵を奪い取ることに成功したと見える。
抗は窓を割って外へ出ると、そのまま気流の中を滑るように舞い上がり、飛空船の全容を視界に収めた。
竜刻の力で動く大きな船は、進路をそれ、樹海の外へと向かっていた。そしてその向こうに――
「海があったのか」
なるほどあそこなら、樹海のただ中に落ちるよりはましだろう。
森のほうを振り返る。
空中での戦いはほぼ決していた。
樹海からは、煙や火の手があがっているところも見え、まだ戦闘が続いている様子だ。
飛空船が失われたことが知れれば、その趨勢も傾くだろう。
ドラグレットとロストナンバーを乗せたワイバーンたちが旋回して、樹海の、まだ戦いが続く地域へと向かうのに気づき、彼もまた後を追うのだった。
*
その後――
パーリアの樹海を舞台に繰り広げられた「ドラグレット戦争」は、この戦いを生き延びたザムド軍側の傭兵たちによって外界の人間にも伝えられることになったが、頭から信用するものはあまりいなかった。
特に、ドラグレットに味方する人間のように見える種族、あるいは見たこともない異形の種族が、魔法のようなわざをあやつり、また、鬼神のような奮闘を見せて公国の大軍を押し返し、蹴散らしたのだという。
果てに、空を舞う竜を見ただのというものまであらわれ、とにかく、激しい戦いだったのだろうということだけは伝わり、あとはただ、ドラグレット族にまつわる、いっそう神秘的な噂が、色濃さを増すことになったのだった。
伝聞はいつしか脚色され、吟遊詩人たちが創作した楽曲がキャラバンの路を通じてヴォロス各地に広まってゆくのだが、それはまた後々のこと。
飛空船がその巨体を沈めた海に、太陽が没したあと。
ドラグレットの集落は、かがり火が煌々と焚かれ、戦の興奮覚めらやぬ熱気に包まれたままだった。
「感謝を述べます、客人たち」
エメルタが心からの礼を言う。
ドラグレットの戦士たちが、最大級の敬意をこめたまなざしで、ロストナンバーたちを見つめていた。
むろんこれほどの規模で、犠牲が皆無ということはありえない。
特に地上での戦いでは命を落としたドラグレッドも多くおり、集落のあちこちでは、呪術師たちが戦士の霊を慰める呪歌を朗々と唄い上げ、戦死者の家族らしきドラグレットたちが大声で泣いていた。
しかしそれさえ、過酷な樹海で生きるドラグレットには、悲しいことであっても、いつかはくるという覚悟の対象であったのだろう。まして戦自体には勝っているのだ。集落の空気は明るかった。
首狩り大将オウガンは上機嫌で、ロストナンバーたちの武勇伝をおのれの活躍のように嬉しそうに語って回っている。
集落を守っていたドラグレットの女たちが用意してくれた――そして椙 安治がせっせとこしらえた食べ物、飲み物が振舞われた。
精霊への感謝の踊りを舞うドラグレットの影が、焚き火に照らされて長く伸びる。
飛空船は堕ちたが、ザムド公がその野望のすべてを諦めたかどうかが、懸念されるところだった。
しかし、冷静に状況を吟味してみるに、莫大な資力を尽くして用意した船と、傭兵の大半を失ったことで、もともと辺境の小国に過ぎないかの国はかなりの傾きを見せているはずだ。当分はその立て直しだけでも窮々となるであろうし、場合によってはこのまま滅びるかもしれない。
そして今回の戦いの話が伝われば、今度こそ、みだりに樹海に踏み込もうなどという人間は、もういなくなるのではないだろうか。
翌朝。
ロストナンバーたちはエメルタに呼び集められた。
「あらためましてお礼を言います。父からみなさんにお渡ししたいものがありますので」
そう言って、派遣隊のみならず、援軍にかけつけてくれたロストナンバーたちを招く。
集落のはずれから森に入り、すこし進む。
そこに、樹木に隠されるようにしてぽっかりと開いた地の底への開口部があった。
エメルタに随行するドラグレットが松明を灯してくれる。
その灯りに導かれ、どれくらい進んだだろうか。
「おお……!」
誰からともなくもれた感嘆の声。
そこは、驚くほど広い、地底の空洞だった。
鍾乳石……なのだろうか、なめらかな石の地面に、石筍がいくつも生え……いや、それだけではない、あれは――。
「ドラゴン」
うたれたように、誰かが言った。
それは骨だ。
壱番世界のコンダクターなら、恐竜を思い出したかもしれないが、その背に残る翼の骨が、単なる爬虫類でないことを物語る。
それは伝説のドラゴンそのもの。その完全な骨格が、鍾乳石の洞窟の壁に、床に、天井に、埋もれるようにして眠っている。
大小さまざまで、おびただしい数である。
これこそがドラグレットが守り続けてきたかれらの聖地。
竜の墓場だ。
――と、いうことは。思いあたって顔を見合わせたロストナンバー。すでに察していたものは頷きを返す。
この地底の空間は、素養あるものならば息苦しくなるほどの魔力に満ち満ちている。
それもそのはずだ。
竜の骨の化石とは、それすなわち竜刻に他ならない。
ちっぽけなひとかけらをめぐって、このヴォロスでは国同士の戦争さえ起きているというのに、ここにはその千倍万倍にあたるであろう竜刻が、ただただ地底のしじまの中で眠りについている。
それはいかに偉大で、厳粛で、恐るべきことか。
ザムド公が我欲のために樹海を目指したのはある意味正しく、もしもこの地を手にいれていたなら、ヴォロスを支配していたのはザムド公だっただろう。
古き種族ドラグレットたちは、かれらもまた、望めばそれが可能なのかもしれないが、決して野心に焦がれることなく、この地を護り、おのれの祖先にしてかつての世界の支配者の骸に畏敬の頭を垂れるだけで、寡黙な墓守の役だけを粛々と務めてきたのであった。
もしもこのことが外界に知られれば、ザムド公どころかヴォロス全土から人間の軍勢が押し寄せることだろう。いかに恩人とはいえ、これほどたやすくロストナンバーを案内してくれたドラグレットはそのことを理解しているのだろうか。いずれにせよ、このことはヴォロスの人々には永遠の秘密にしておかなくてはなるまい。
「これを、みなさんに」
洞窟の一部はわきだす地下水に没しているようだった。
その岸で、呪い師たちがなにをしているのかと思えば、水の中から石を拾っているようだ。
「聖地の水で磨かれた石に、呪術文字を刻ませます。これは幸運をもたらす守り石です。ええ、そう。エドマンドにもあげたものです」
守り石は、派遣隊と、援軍に来てくれたロストナンバー全員に、ひとつずつ渡されることになった。
名残はつきぬが、いつまでもいるわけにはいかない。
その日のうちにロストナンバーたちは集落をあとにし、帰途へとついた。
いつかまた、ここへ帰る日もくるかもしれない。この石があれば、帰ってこれるだろう。
旅人を導くのはいつだって、運命という名の風だ。
ふと交わり、過ぎ去って、そしてまた、吹きゆくのである。
(了)
![]()









