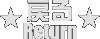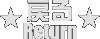|
<ノベル>
星――、だろうか。
銀幕市とおぼしき街の上に、黒々とわだかまる夜空。
リオネはそこに、7つの星を見た。それはどこか不吉な輝きだ。
リオネが見ている前で、それは次々と流星になって市街に降り……、その中にまぎれていった……。
「……?」
奇妙な夢から目覚めて、あくびをひとつ。
窓を開ければ燦々とふりそそぐ朝日。今日も銀幕市は平和――ではなかった。
★ ★ ★
ついにその日がやって来た。
岡田剣之進が挑戦を受けて立つ日である。その掲示を見かけたときから、武士として受けた挑戦には応じねばならぬと……、彼はそう考えていた。
愛刀を手に、一歩を踏み出す。剣之進の向かった喫茶店の店頭には『巨大パフェ 挑戦者求む! 10分以内に食べたらタダ!』の文字。
「頼もうーーー!!」
しかし――
「すいません、今日は材料がなくて……」
店員のその申し訳なさそうな一言で、剣之進の意気込みはすっかり出ばなを挫かれてしまったのだった。
そのうしろを、こそこそと、小さな影が逃げていく。
「おぉーまァえ……かァァァアア!!!!」
道を行く兵士の一団を発見するやいなや、クレイジー・ティーチャーが咆哮をあげて飛びかかっていく。
「ジョーダンじゃないヨ、あとで食べようと思って大切にとっといたプリンなのにサ!?」
「私のデザートに手ぇ出すなんていい度胸してるじゃない……! バッキー印のはちみつプリン、なかなか売ってないんだからねー!!」
いつのまにか、浅間縁も一緒になっているが、つまるところ、ふたりとも、件の連中に甘味を奪われた仲間であった。
「言いなヨ、どこの命知らずに頼まれたのカナ!?」
いつにも増して凄まじい形相で迫るクレイジー・ティーチャーだったが、勢いあまって投げ付ける金槌や、まきちらす塩酸によって、兵士たちは捕らえられる以前に粉砕されてあえなく戦死を遂げていくのだった。
「ボクの……おやつが〜、おやつがな〜ぁいっ!!」
「盗まれたですって!? 酷い……楽しみにしてたのに!!」
「許せないね。甘味はとても貴重で尊いんだよ。甘味ひとつ買うためにどれほどの決意をしたと」
バロア・リィムの、夜乃日黄泉の、続歌紗音の、怒りと悲しみの声。
同様の叫びは、銀幕市のあちこちで聞かれた。
そしてみな、誓った。不届きな犯人を必ず捕らえてみせると。
「ぜったい、ぜったい、ゆるさないですぅ! ちょこれーとも、ぷりんも、びすけっとも、みんなみんな、なくなっちゃって……!!」
杵間山の麓――、ブラックウッド邸においても、ブラックウッドの使い魔が、先程からいたく憤慨した様子で、黒い翼をぱたぱたやっていたのだが。
「それは大変そうだねぇ」
当の主人は、安楽椅子にかけたまま、読んでいる本から目もあげずに、気のない返事しかしてくれなかった。
「ごしゅじんさま……!! にんげんのたべものはめしあがらないからって、たにんごとなのです! ……なら、じぶんでどうにかするです!」
そして、ぷい、と飛び立っていく――。
いつまでも、この理不尽な略奪に、されるがままになっている銀幕市民ではなかった。
「捕まえたわ」
「ど、どうやって!?」
沢渡ラクシュミの手の中で、ちいさな兵士がじたばたしていた。
「すごいです。私も挑戦してみたんですけど……」
中河忠匡の作戦は、ポケットにお菓子をつめて街を歩いてみるというものだった。それを奪いにきた兵士を、コートでくるんで捕まえようとしたのだが、なかなかどうして、連中はすばしこい。
「ゴキブリホイホイに角砂糖を置いておいたの」
「そんな方法で!」
忠匡が驚いていると、もうひとり、兵士を捕獲したらしい西村がやってきた。
「あなたはどうやって?」
「……棒で……支えたザルの……下に……お菓子を置いて……」
「……」
意外と原始的な方法のほうが有効なのだろうか。
「何……で、こんなこ……と、した……の? 欲し、いなら……ちゃんと言えば……あげ、る、のに……」
西村は語りかけるが、兵士からいらえはない。話せないのだろうか。
★ ★ ★
情報は、人々とともに、カフェスキャンダルに集まる。
残念ながら、自慢のスイーツを食べることはできないのだったが。
「とりあえず、業者に連絡して、騒ぎが落ち着くまでは市内に菓子の原料を仕入れるのをストップさせている。品薄になるし、売上も打撃を受けるだろうが、盗まれてしまうよりマシだからな」
と八之銀二。
「兵隊ということは、指揮をしているものがいるはずだ。やつらが奪ったものをどこに運んでいるのかがわかればいいのだが」
アラストールが言った。彼はすでに20体以上、チョコ兵士を斬り捨てているが、それでは埒が開かないと思ったようだ。
「あのー」
そこへ梨奈が声をかけてきた。
「お店にこんなFAXが来たんですけど」
梨奈が差出したFAX用紙には、なにかの画像がプリントされていた。
「ほう、これは監視カメラの画像だな。ここに連中が写っている」
さっと用紙を奪い取って、マックス・ウォーケンが言った。
「これで連中の逃走径路がわかるぞ。僕の持っているかれらの出現地点をしるした地図と合わせれば……」
マックスがカフェのテーブルに地図を広げる。その地図はマックスが電車の中でうたた寝をしているあいだに、いつのまにか脇に差し込まれていたものだった。FAXについては、白姫なる謎めいた存在から送られてきたものなのだが、それについては、誰も知るよしもないことだった。いずれにせよ、有効な手がかりと思われた。
「んん、みんな頑張ってるねぇ」
そんな様子を横目に、優雅に紅茶のカップを口に運ぶエンリオウ・イーブンシェン。
「甘味がたくさん集められている、ところ……か」
彼の片手の中で、ティースプーンがすっと浮かびあがり、まるで方位磁針のくるくると回りはじめる。そして、やがて、ある方角を指してぴたりと止まった。
「ギャ、ギャッ!」
来栖香介のバッキー、ルシフが、兵士を押さえつけて、みしりと、その腕をひきちぎった。投げ出された腕は、片山瑠意のまゆらが、むしゃむしゃと食べてしまう。ある意味、おそろしい場面ではあるのだが、血などが出ないのでだいぶ救われている。
その傍で、買い主たちは、テーブルにつき、事件についてああでもないこうでもないと考えを巡らせるのだった。
「あいつらもチョコでできてるんだな……俺たちも食おうと思ったら食えるのか。踊り食いはどうよ?」
「お菓子でできた兵士……そうだ、犯人はパティシェだ!」
「……目的は?」
「集めたチョコを小判のようにバラまく?」
「ネズミ小僧かよ!」
「いや……もしかしたらミリタリーマニアかも……」
「ははは、仲間増やして侵略の準備してたりしてなー」
香介は笑った。
そのときはまだ、その言葉は軽口に過ぎなかったのだが――。
白神弦間は、鼻をひくつかせた。
周囲には、妙に甘い匂いがただよっている。
「……」
ブラックライトに浮かび上がる足跡は、確かに、その塀の向こうへ消えていた。
彼は、ケーキのまわりに蛍光塗料のワナを張ったのだった。その塗料はブラックライトのもとでだけ光って浮かび上がる。兵士の残した足跡を、それで追うことができた。
「ここが、あのありんこ兵士の巣……かいな。女王でもおるんかいなぁ?」
そこは、湾岸の工場地帯のさらに外れの、人通りも少ない地域だ。ぐるりと周囲をめぐってみるが、敷地は広い。しかしながら、塀の向こうにあるのは、外から見る限り人気のない廃工場のようだった。
「お?」
弦間は、すこし離れたところに、太助の姿をみとめた。
弦間が知恵を使ってここを突き止めたのに対して、タヌキ少年は、地面の匂いを嗅いでいる。野性の嗅覚によって、ここまでたどりついたようだ。
「こっちのほうだな……? んっ――」
「わああああっ」
下ばかり見ていた太助が、どん、となにかぶつかった。
ぶつかられて、声をあげたのはクラスメイトP。
彼は太助に事の次第を語った。Pは、配達中のあんまんを奪われて途方にくれていたところ、いつしか思考は現実を逃避して、チョコ兵士たちの行く先に対する空想にとらわれてしまっていたのだった。それで、コンペイトウをバラまいて、それを持ち去った兵士のあとを根性でつけてきたのである。
「甘いもの、探しに来たの……?」
空とぶ金魚に匂いをたどらせてきたトトが、ふたりに声をかける。
「とにかく、入ってみようぜ。きっと中には……」
太助の中にも、もやもやと想像が広がる。銀幕市中から集められたお菓子の山があるはずだ。
「あ、こら、坊主たち……あんまり無茶すると……あーあー、入っていっちまった。……人を呼んだほうがいいかね」
ぼりぼりと、弦間は頭を掻いた。
★ ★ ★
さながら少年探偵団――、太助、クラスメイトP、トトの3人は、塀の崩れた穴から敷地に忍びこむ。中に入ると、いっそう、甘い匂いが強くなった。
建物の裏口から、そっと中へ。
するとそこには……!
「!?」
予想だにしない光景だった。
お菓子の山だ。いや、それは予測されたものだった。
「すごいねぇー、こんなにいっぱい。でも、ヒトのものとっちゃいけないのに」
トトが、そんな素朴な感想をもらした。
銀幕市中から集めてこられたとおぼしき、ありとあらゆる甘いものが、そこにはあった。
チョコレート、クッキー、プリン、ケーキ、シュークリーム、まんじゅう、どら焼き、たい焼き、羊羹、カステラ、そして、袋のままの砂糖まで――。
そしてその真ん中で。
「しあわせだにゃ〜」
クロノがだらりと伸びて、手当たり次第に、周囲の甘味を口に運んでいるのだった。
「おまえが犯人かーーー!?」
「にゃっ!?」
太助に飛びかかられて、猫神ははっとわれにかえったようだった。
「いかんにゃ。うっかり、つまみ食いに夢中になってしまったにゃ。にゃんともはや、カフェにあらわれた兵士の時間を巻き戻してここをつきとめたまではよかったのですにゃが……ほんのちょっと味見させてもらうつもりが、なんかやけにノリよく……」
「なはははは、みんなノリノリアルよー!」
半透明のなにかが横切って行った。
「あれのしわざか……」
「あっ、みなさん! こんなところに!」
どこからか入り込んだらしいコウモリ――ブラックウッドの使い魔があらわれた。
「やりましたのです! ついに奪われたお菓子をみつけたです!」
「しっ、みんな、声が高いよ。誰かに見つかったら……」
遅かった。
目を刺すサーチライト。
そして、はげしい銃撃音!
「わわっ」
「に、逃げろ!」
バラバラと、足音を響かせて、チョコレートの兵士たちが侵入者を追った。こんなにいたのか……と思うほど、かれらはあちこちからあらわれ、その数を増やしていった。
「に、逃げるってどこへ!」
「どこでもいい!」
退路を絶たれ、とにかく、走れる方向へ走る。
太助が、だん、と扉を蹴り開けた。
そこには――
「!!」
なんだこれ。
クラスメイトPは目を見張った。
その時まで、彼は思っていたのだ。兵隊にお菓子……まるで、くるみ割り人形の道具立てだ、と。きっとどこかにお菓子の国でもあるのではないか、と。
だが、思い描いていたメルヘンは、どこにもなかった。
そこでは、ごうんごうん、と音を立てて、得体の知れない機械が作動していた。
何台もある。文字通り、ここは工場だ。
機械は、無造作に、大量の菓子を飲み込んでいた。そして、ふるえたり、唸ったり、蒸気を吹いたりといった工程を経て、反対側のベルトコンベアーのうえに、それらを吐き出している。
それは小さなサイズの、黒光りする銃であったり、かわいらしい飾りもののような手榴弾であったりした。中には、戦車や戦闘機とおぼしきものもある。もちろん、迷彩の戦闘服の兵士たちも、また。
かれらは、しばらく、その光景にうたれたように立ちすくんでいた。
これは、兵器工場だ。
戦争を行なうための準備が、着々と進められているのである。
「侵入者か」
大音声で、誰何の声がかかった。
だん、と、機械の上に、それが立ち上がる。
ばさり――、とひるがえるマントの下に、近世ヨーロッパの肖像画にあるような、クラシカルな軍服があらわれた。
「誰だ、おまえ!」
太助の声には応えることなく、それは、かれらを睥睨している。兵士たちとは違い、かれは人間とかわりない大きさで……むしろ長身であった。その肌はチョコレート色。ぴんと尖ったカイゼル髭も、どうやらビターチョコレートでできるのか。ならば、白目の部分はホワイトチョコなのかもしれなかった。
「もうすこし充分な軍備を整えてからと思ったが……やむをえんな」
それは、軍服の手をさっと掲げた。まるでなにかを命じるように。
「雲行があやしい。ここはいったん、逃げたまえ!」
使い魔から、ブラックウッドの声が降ってきた。
だが、ザッザッと軍靴の音を響かせて、兵士たちが迫ってくる。
「こっちだ!」
ぱん、と手を叩く音。それを合図に、兵士たちの歩みがぴたりと止まる。
だん、とドアを開けて、エンリオウが叫んでいた。
★ ★ ★
地響き――。
クラスメイトPたちが脱出したのと時を置かずして、廃工場は、ばらばらと、古ぼけたその外見をかなぐりすてていく。
見る間に、パイプが伸び、新たな壁ができ、煙突がはえて……そこに新しい工場が、早回しで植物が成長するのを見るようにできあがっていった。
それだけではない、さらなる地響きとともに、それは、ゆっくりと「立ち上がった」のである。
銀幕市中に、甘い匂いが漂っていた。
うっとりするような、それはチョコレートの香りだ。だが、誰も、その香りに心躍らせているものはいなかった。なぜならばその匂いのもとが、目下、銀幕市に脅威をもたらしているからだ。
ズシン、ズシン、と重い地響きが、市街をふるわせる。
昆虫めいた3対6本の脚で、それは立ち上がり、歩んでいる。脚が支えているのは、いくつものパイプやタンクで構成されたプラントのようなものだった。いくつも煙突らしきものが突き出し、そこからさまざまな色の煙を吐き出している。それが甘い匂いのもとであるらしかった。
それは大きな工場がひとつ、脚をはやして立ち上がったようなしろものだ。かのキノコ怪獣さえしのぐ大きさのものが、湾岸の工場地帯から、街の中心部のほうへ向かってくるのを見て、いよいよ銀幕市も終わりかと、青くなったものも少なくない。
「『お菓子の国の冒険』というメルヘンチックなファンタジー映画からあらわれたようですね」
植村直紀が手元の資料を見ながらいった。
「あれは『キングスファクトリー』といって、『チョコレートキング』が住むお城であり、彼のお菓子工場でもあります。……映画の設定では、チョコレートキングは温厚な人物ですし、あれも、各地を旅しながら子どもたちにお菓子を配っていくという……そのためのものなのですが……」
困惑気味に話す。
どこでどう間違ってしまったのか、キングスファクトリーは夢のお菓子工場ではなく、いまや要塞であり、兵器工場であり、敵軍の母艦のようなものだ。
敵軍――。
そう。それはときおり、バラバラと、その工場で「生産」されたとおぼしきものを吐き出しながら歩んでいる。それは文字通りの「お菓子の兵隊」たちであって、それらが引き起こす事件や被害についても、先ほどからひっきりなしに『対策課』に飛び込んできていた。
「私は市街地で起きている事件の処理を手配します。……あれについては、マルパスさんにお任せするべきですね」
植村は、黒衣の司令官にそう言うと、現状、入手できただけの情報を記したファイルを置いて、忙しそうに駆け出していった。
そしてマルパスは市役所の窓から、いまはまだ遠い『キングスファクトリー』の影を見据える。
まぎれもない「戦争」が、銀幕市ではじまろうとしていた。
|