カンダータ訪問団
![]()
![]()
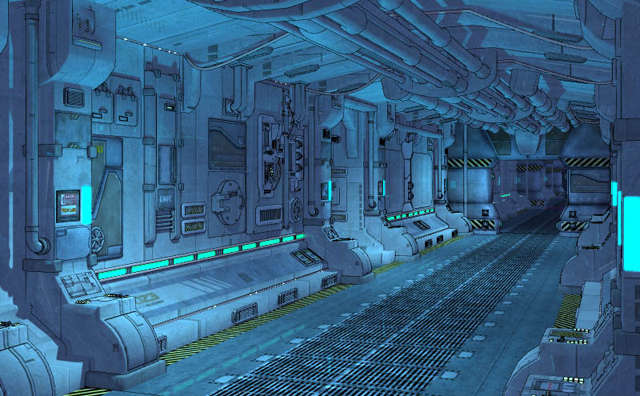
![]()
 『理想都市ノア』観光視察
『理想都市ノア』観光視察
■食糧工場
ごうん、ごうん、と音を立てて、機械の群れが唸りをあげている。
「へーっ、あれが合成食糧ですか? コンビーフみたいなものかな?」
藤枝 竜が見学路のガラスに顔をくっつけんばかりにしてフロアをのぞきこむ。
ベルトコンベアーの上を、整然と、肉のかたまりのようなものが流れていくのが見えた。
フロア内には作業服の工員たちが大勢、それぞれの持ち場で働いている。
「工場には軍の視察ということで話してありますので」
案内の兵士がそう説明してくれた。
「ここは公営で、配給を行う食料品や、軍の糧食などをつくっています」
ちょうどそのとき、サイレンがなって、いくつかのラインが停止する。
工員の休憩時間のようだった。
「見えないよー……むぅ~……!」
マグロ・マーシュランドは身長が足りなくて、窓まで届かず、フロアが覗けないでいるらしい。
「あらあら。だっこしてあげましょうか」
見かねたアイヴィーに抱き上げられて、ようやく工場を目にすることができた。
マグロの瞳が輝く。
「おぉ~っ、お肉だ~♪ ねぇねぇー、アレどんな味がするのー? 食べてみたいなー。良いかなー?かな~??」
「休憩時間ですね。降りてみますか?」
案内の兵士とともに、フロアへ。
試食用にと、そのブロック肉のようなものを渡される。
「いえ、わたしは遠慮しておきますぅ~」
と断ったアイヴィーだが、肉がどんなものかは関心がある様子だ。
「ん。なかなかおいしいですね。カンダータは食の分野でも油断ならないですね~」
竜は合成肉を味見してそんなことを言った。
マグロはアイヴィーに出されたぶんもむしゃむしゃと食べて満足げ。
「これ何でできてるの?」
「家畜の肉を化学物質で加工しているのです」
マグロが質問をしているあいだ、竜は、休憩中の工員に話しかける。
食べ物以外も配給されているのか。政治や社会制度に不満はないか。
「最近は食糧品以外は自由に買えるようになってるんですよ」
「私たちは仕事があるし、恵まれていると思います」
そんな答えが返ってきた。
■ショッピングモール
物を売っている場所や、庶民の一般的な暮らしを見られる場所へ行きたいと希望するものは多かった。
案内の兵士がすこし考えて連れてきてくれたのは、大勢の一通りがあるアーケードの下、ショッピングモールのような場所だった。
「ここで食糧品も手に入るの?」
ディーナ・ティモネンの問いに、兵士は頷く。一部の物資は配給によるが、できるだけ配給品は減らして自由経済への移行を進めようとしているらしい。
食糧品だけでなく、さまざまな小売の店が並んでいるので、ここを見ていけば、ノアで出回る品物がどんなものか把握できそうだった。
「……」
ディーナは買い物をしている人々の様子に、いくぶん安堵したような眼差しを見せる。予想したよりも、人々が自由そうに見えたからだった。
「衣類や雑貨もありそうですね」
流芽 四郎が、そしてカナティア・マティアが目当ての商店をもとめて視線を巡らせた。
「全体主義から、ほんの少し変わり始めたばかり――、というところかな」
ショッピングモールの賑わいの中を歩きながら、ディーナ・ティモネンがぽつりと言った。
「それにしてもなんか、やっぱり日本と比べて空気がぴりぴりしているような気がしなくもない? いや、自分が緊張しているだけか」
と小竹卓也。
幾人かのロストナンバーたちは積極的に商店に足を踏み入れる。
「これ何? どうやって食べんの?」
ジル・アルカデルトは野菜を売る店をのぞいていた。
店頭に多く並んでいたのは、おそらくカブに近い野菜で、生だと硬いので煮てたべるのだと教えてもらう。
流芽四郎は鞄などを扱う店で皮革製品を検分していた。以前から得ていた情報のとおり、大半は合皮のようである。
「……失礼。革を商っているものですが……」
店主に、ブルーインブルーの海魔の皮を用いた自作の手袋を見せる。
「これは見たことのないものだ。……え、値段? うーん、そうだねぇ。天然といったって何の動物かわからないとねぇ……」
天然の皮革は高値と聞いていたが、質自体は合成皮革も劣らないものであるため、天然ものの価値とは人々がそれが天然と認めるかどうかにかかっている。ならばカンダータの生き物の皮でなければ、高値に売るにはなんらかの工夫がいるかもしれない。
カナティア・マティアも織物を見ていたが、
「ね、この繊維はなんというものかしら」
「これは14番ですよ」
毛織物も、人工の合成材料がほとんどのようだ。
「天然のものはないの?」
ダンジャ・グイニが尋ねるが、
「うちはあまり扱ってないんです。高くて買う人も少ないから」
と返ってきた。
もっと高級品を扱う店は、それなりの層の人々が住む地域にあるらしい。
「このへんの人も貧乏には見えないけどね」
華城水炎が言った。行き交う人々を観察していたのである。
ディーナ・ティモネンもそれには同意だ。
「品物の数も種類も豊富だ。経済状態はいいように思うが」
「この都市に来た記念になりそうなものって、なんかあんの?」
水炎が土産ものをもとめて店に入った。
これはどうだい、と薦められたのは、額に入った壮年の男性の肖像画だった。なんでも「建国の父」らしいが、水炎の目にはただのハゲたおやじにしか見えないのだった。
■緑化地区(高台の公園)
「植物園や森林公園のような憩いの場ってあるのかしら」
ホワイトガーデンたちが案内されたのは、緑ゆたかな公園のような場所だ。
木々のあいだを遊歩道が行き交い、広場には噴水がある。その周辺では子どもたちが駆けまわっていて、ここはノア市民たちが訪れる憩いの場所といった風情である。大道芸を披露している芸人たちの姿も見ることができた。
「いい眺めですね!」
リーミンが柵から身を乗り出さんばりにしている。
この公園はノア市の地上部に近い、いわば「高台」にあり、辺縁からはノア市内を一望することができた。
機械で埋め尽くされた地下都市の中にあって、この周辺だけは空気が澄んでいるような気がする。そうした浄化作用も兼ねているのかもしれなかった。
「えー、そんな……困ります」
「まあ、そう言わずに、ちょっとお茶だけでも! ね!」
烏丸 明良が、訪れていた女性市民に声をかけていた。相手の女性は困っているようだが……
「だ、だめですよっ、女の子を困らせたらメッですからね?」
七夏がナンパを止めに入ってくれた。
そそくさと女性は立ち去る。
「……でもナンパでなくて、お話を聞くくらいなら……」
おどおどしながらも、周囲を見回し、声を掛けられそうな人を探す。
見れば、大道芸人の周囲に人が集まっている。フォッカーもそこにいるようだ。
「どこで習ったのかにゃ? サーカスみたいな一座ってあるのかにゃ?」
ジャグリングをしている芸人にフォッカーが話しかける。
「俺はノアで商売してるけど、町から町に廻っている連中はいるよ。前線に慰問に行ったりね」
ジャグラーは応えた。
「でもノアがいちばんさ。平和だしね」
そんな様子を横目に、エルエム・メールは自身で踊りを披露して人を集める。
「最近の暮らしはどうなの?」
「どうって……、あなたはよそから来たの?」
市民の言葉に話を合わせ、そうだと答えれば、
「そう。大変ね。よそはいろいろ苦労が多いっていうわ。あなたもがんばってノアの市民権が手に入るといいわね」
そんなことを言われた。
青燐は、その能力を活かして公園内の植物から情報を集める。
公園ができてから今までの様子を、植わっている植物に尋ねてみたのだ。かれらの話を総合してみても、ここが平穏な町なのは間違いないらしい。少なくとも、戦争のようなものが起こった様子はなかった。
「こんな風に、この世界の人達も休みの時はゆっくりと過ごしてるのね」
ベンチに腰掛け、ホワイトガーデンが言った。
「ね、この花はなんと言うのかしら」
案内の兵士に聞いてみる。
「……花の名前なんか知らん」
「あら」
ふっ、と微笑む。
「あなたもお休みの日は散歩したりしないの」
「……ノアは平和な場所だ」
質問には答えず、兵士は言った。
「この町を守る仕事に就いていることを自分たちは皆、誇りに思っている……」
高台から町の様子をひとしきり眺めていたリーミンは、今度は木に登ってさらに高い場所を確保した。
ノアの町は、建築物の屋根をさらに足場にして道路を走らせるなど、複雑に町が積み上がっていくような構造になっている。木の枝に鳥の巣でもないかと探したが、見当たらないようだ。小さなマキーナでもいたら面白いのに……そんなことを考えてみる。
「やっぱ、こーゆう所は落ち着くわよね。なんつうか、心が安らぐって感じ? ……あら、シャワー付のプールまであるじゃない。なかなかイケてるわねここ」
そう言ってフカ・マーシュランドが躊躇もなく、噴水の中にざぶざぶと入っていく。
ここで弁当を食べようと包みを広げ、持参した魚へ「あーん」と口を開ける。
「……なーに見てんのよ?アンタにはあげないわよ」
着ぐるみかなにかと思われているのか、奇異の目を向ける通行人を威嚇。
小動物の形態で酔ってきた宇宙暗黒大怪獣 ディレドゾーアにも、シャーっとキバを向くフカであった。
■学校
「ふーん、見た感じ、壱番世界と変わらないな」
虎部 隆の、初見の感想はそれだった。
「できれば生徒と話がしたいんですけど」
一ノ瀬 夏也が言った。
そこは市内の学校である。ここでは6歳~18歳の男女の生徒が教育を受けている。壱番世界風に言えば小中高一貫という形式だ。今日は軍関係者の視察があるということになっていて、生徒に話しかけてもいいそうである。
「じゃあ、オイラは小さい子どもたちと触れ合うのにゃ」
ポポキが言った。
「私は……中学生以上の生徒と話してみたいかな」
と、夏也。
「授業を見学しても?」
隆の問いに、案内の兵士は頷く。
途中、廊下の向こうから、幼い子どもらの声がかかった。
「軍人さーん!」
苦笑しながら、案内の兵士が手をあげて応える。軍人は、子どもたちに人気があるらしい……。
「12歳、15歳、18歳向けの、道徳、修身、教練等にあたる教材と、その担当教諭の
話を伺いたい。俺は…この世界が、子どもたちにどんな思想を与えているかを聞きたいん
だ」
それが坂上 健の要望だった。
まずは職員室で、教科書を見せてもらうことができた。だいたい共通して、皆で協力し合うことがいかに大切かということを説いているようである。
「……なにか聞きたいことがあると?」
一人の男性教員が連れてこられた。
「失礼ですが……貴方は予備役相当ですか?」
「それが何か」
「子どもたちに、何を尊び、何を敵とし、どう生きるのが正しい生き方だと貴方がたが教
えているか……俺が知りたいのはそれだけです」
「どういうことでしょうか。むろんノアの理想主義を教育しています」
こちらを軍関係の視察と考えている教員は、なぜそんなことを聞かれるのか訝しげだった。
「教材ではどれも軍の仕事は尊敬されるべきものだと」
「当然です。そうでなくて世の中は成り立たないのですから」
「子どもたちは素直に聞いていますか?」
「そう信じています。……ただノアの子どもたちは、他の都市に比べれば危機感が足りないのは事実です。そこはもっとしっかりしなければと思うのですが……」
休み時間になった。
校庭で走り回る年少の子どもたちの中に、ポポキや板村美穂が混じっている。
美穂は授業の見学から入っていたので、クラスの子にあっという間に溶けこみ、特に彼女のハムスター型のリュックが小さな子どもたちの間で人気を博すのであった。
「みんなのヒーローってどんなのかにゃ?」
ポポキが尋ねると、みなが口々にあげる名は、どうやらテレビで観る番組の登場人物などであって、そういったところは他の世界の子どもたちと変わらないように思えた。軍人の名があがるかと思ったが、年少の子らはそういったことまでは知らないようだ。
「ね、競争しようか」
美穂の提案で、駆けっこが始まる。
そんな様子を横目に、森間野コケは、校舎脇の花壇に植えられている植物を熱心に眺めている。壱番世界にもあるような植物がほとんどだが、コケはそれが人工的に培養されて、調整された地下都市の環境下でのみ生きられるものではないかと感じ取っていた。カンダータは、都市をでれば過酷な寒冷地だ。自然環境は豊かとは言えない。
さて、グラウンドの別の一画では、これもいつのまにか同年代の生徒たちと意気投合した虎部隆が、バスケットボールに興じているのだ。
その様子を、一ノ瀬夏也がポラロイドに収める。
吐き出された写真は、ごくありふれた学生生活の1コマのようだ。
「へえ、それじゃ今はそのナターシャって歌手が人気なんだな」
軍人たちより、同年代の学生のほうが話しやすいのは当然だ。男子生徒が携帯端末に保存した画像を見せてくれる。最近、流行しているという女性歌手の画像だった。
「卒業したらどうすんの?」
話した感じ、まったくごく普通の十代だと隆は感じていた。ただ、なにげなくそんな質問をしたところ。
「オレは軍隊に入るよ」
「オレも」
「軍はムリかもだけど、国の機関で働きたい」
そんな答えが口々に返ってきたのは、やや面食らった。
「……家族が軍で働いているっていう人は多いの?」
夏也も、女子生徒をつかまえて訊ねてみた。
「うちのお父さんもそうよ。クラスにも、他に何人もいるけど」
「そうなの。……心配じゃない?」
「少しはね。でもノアにいる間は大丈夫」
少女は答えた。
「あなたは将来はどうするの」
「まだ考えてないわ。でもお母さんは軍の事務員をしていてお父さんと知り合ったの。そういうのもいいかなあって思ってる」
「そう」
壱番世界の子どもたちとの違いを強いてあげるなら、軍隊の存在がごく身近に、自然にあるということに尽きるだろう。そこに悲壮さは感じられないが……もっと戦地に近い町なら、事情は異なるかもしれない、と夏也は思った。
■新聞社と図書館
新聞社が見てみたい、と言ったフェリシアたちを、兵士は望みの場所に連れてきてくれた。
「図書館へ行きたいという人もいましたね」
兵士が問うと、クアール・ディクローズが頷いた。
「この『ノア第一通信社』は、付属の資料室を図書館として一般に開放しています」
図書館には、一般に手に入るものなら、どんな分野のものでも目を通すことができるだろう。
新聞社に興味があれば、記者たちに会うこともできるようだ。
この場所には、ノア市の情報が集積していることになる――。
「……」
高城遊理は新聞をかたっぱしからあらためてみたが、どの新聞にも異世界に関することは一文字たりとも書かれていなかった。新聞をあきらめ、記者に質問してみるも、どうにも要領を得ない。どうやら異世界方面戦略については、一般には情報が公開されていないらしい。
フェリシアはノア市の地図をもとに、地域の概略などを把握したあと、マキーナについて記者たちの知っていることを確かめてみた。
従軍取材の経験のある記者を紹介してもらう。
「マキーナについて研究している人なんかはいないんですか?」
「軍ではやってるだろうね」
「なにか仮説のようなものはあるんでしょうか」
「さあ……わからないことが多いから。でも連中が連中自身で仲間を生み出しているのは確かだからねえ。どこかにマキーナが生まれる場所があるんだろうとは言われているよ」
一方、付属の図書館では、ディブロが学会誌などにキルケゴール博士の名前がないかを探していた。
おそらく本人のものと思われるいくつかの論文が見つかったが、まだ若い駆け出しの頃のもののようで、とりたてて特異なものではない。軍属になって以降の仕事については情報公開がされていないようだ。
「なにか見つかった?」
アルド・ヴェルクアベルが、クアール・ディクローズに話しかける。
クアールは大判の百科事典のページを指した。
載っている写真は、厳しい顔つきの、禿頭の男である。
「これが『指導者ゴーリィ』。簡単に言うと、カンダータは都市国家がそれぞれ独立していたのを、この人が連邦制という形でまとめあげたって話」
ゴーリィは市民全員が都市の機能を分担し、一致団結してよりよい社会をつくりだす『理想主義』をとなえ、それを反映する社会体制をつくりあげた。壱番世界の歴史に照らして言うなら社会主義が近いだろう。
クアールは軍関係の有名人の情報を求めたが、ミラー大佐でさえ、全体で見れば有名人というわけではないようで、報道などに名前を見つけることはできなかった。
アルドのほうはカンダータの技術について調べたが、これは訪問団が以前、軍の資料室で得た情報と大差のないものだった。おおむね壱番世界の基準に近く、しかし地下生活を送っているため、それに関して発達したと思われる技術などが目立つといったところか。
「この展開は想像しなかった。作家として負けていられないな……」
イェンス・カルヴィネンは宗教について調べていたはずだが、いつのまにか、物語を読みふけっている。
春秋冬夏もだ。
どんな世界でも、物語に人が救いを見出すこともあるのだろう。民話の類は、一家の長老が暖炉のそばで子どもたちに語って聞かせ、受け継がれてきたものが、今こうして本に書き留められているらしい。
■屋内農場
「食べられる穀物や、野菜を栽培しているところを見たいなっ!」
と、黒燐。
「ぼくも興味がある。地下で、どうやって育てているんだろう」
ディガーも応じた。
かれらが案内されたのは、都市辺縁部の「屋内農場」だった。
ディガーの心配はよそに、仕切られた区画には土が十分にあり、そこで野菜が栽培されているようだった。天井では光り輝く水晶のようなものが付いていて、それが太陽の役を果たしているようだ。
ここでは家畜も飼われているらしく、ときおり、動物の鳴き声らしきものが聞こえてくる。
作業服の男女が、それぞれの作業に従事している。
音がしたので視線をあげると、スプリンクラーのようなものが水をまきはじめたところだった。
「あ、ちゃんと土がある!良かったー。全部水耕栽培だったら、どうしようかと思ったよ」
ディガーは嬉しそうだった。
脇坂一人が、水を吸って湿り気をおびた土を手にとり、手ざわりや匂いを確かめる。
「いい土です。ここまで来るのはきっと大変だったでしょうね。肥料は何を?」
「合成肥料ですよ」
農場の人が手を止めて質問に応えてくれる。
ここではジャガイモに似た根菜をつくっているようだった。
「ここで働くのってなんか資格とかいるのかな?」
黒燐の質問には、
「作業だけなら誰でも。技師は大学を出ないといけないけれど」
「ここの農場で、どれくらいの量をまかなえるの?」
「それほどでも。ノアはよその町からも野菜は輸入しています」
「……あの水晶が、太陽代わりかよ。すげーな」
日枝 紡が言った。
屋内農場の天井につけられているそれは、ノア市自体の空である岩盤についているものと同質のもののようで、どうやらこれが、カンダータの人々の暮らしを照らし出す太陽の役目を果たしているようだ。
「陽光石」と呼ばれている特殊な鉱石で、微弱な電流を流すことで暖かな光を発光するそうである。
「あれ、夜になったら消すのかな?」
ディガーの質問にはもちろんそうだと返事があった。
「陽光石」はカンダータの地下都市ならどこにでもあるもののようで、軍の視察としか聞かされていない農場の作業員は、なぜそんな常識にあたることを聞かれるのか不思議そうだった。
「あれって牛なの?」
リオン・L・C・ポンダンスが、鳴き声を牛のたくさんいる場所を見つけ、声をあげた。
ここでは乳牛を飼っているそうである。
熱心にメモをとるリオンの傍らで、ロドヘリクも畜産に興味がある様子だ。食料としてはどんな動物が飼われているのかと問うたが、壱番世界とあまり変わりがないようである。ただやはり、全般的に食肉や野菜をそのまま食材として用いるのはぜいたくなことであるようだった。この農場もさほど大きな規模ではないが、単価が高いために大きな利益を生んでいるようなのだ。
ディガーは、なつかしい土の匂いを味わいながら、コンパクトな耕運機で畑が耕されているさまを飽くことなく眺めている。
■ノア市警察署
「軍は国を護るための機関……。では国の治安を維持し護る、警察機関、もしくは自警団のような機関はあるのかしら?」
流鏑馬 明日の質問に、もちろん警察はある、と兵士は応えた。
明日たちはノア市の警察署を見学することになる。すんなりと見学が許可されたところを見ると、軍と警察の関係は悪くないと推測できた。
大柄な警官が、ロストナンバーたちを出迎えた。
「署内を見ても面白いことは何もないだろう。これから市内のパトロールに出るので、一緒に来るかね?」
「迷惑にならない程度にご一緒します……」
流鏑馬明日は申し出に応じることにした。
「ワシもいいかな」
「…エット… コンバンワ…オ巡リサン…ボク、幽太郎ッテ、イウノ…宜シクネ…」
風間剛志に、幽太郎・AHI-MD/01Pをはじめ、幾人かのロストナンバーが巡回に同行することになる。
「私も警察官なので……もし役にたてる事が有れば良いと思って」
明日は、ノアの治安について知りたかったのだと話した。
「ノア市は平穏なところだよ。まあ、人口が多いので起こるトラブルはあるがね。おっと、こいつは違法駐車だ」
「ドカセタライイ? 任セテ!」
幽太郎が駐車違反の車を牽引する。
「どうして警官になったんです」
相沢 優が質問した。
「市民はなにか国の役割を担うべきだからね。軍に入るか迷ったんだが。……コラ、この車はキミのか」
幽太郎にどかされた車の持ち主が慌てて駆けつけてきたようだ。
「……」
市民の様子からして、警官は恐れられているようだと優は思った。
「どんな理想を抱いていたんだろうね」
「え?」
「理想の名のもとに建設された『理想都市ノア』……でしょ?」
枝幸シゲルは微笑った。
道行く人々は、警官が通ると居住まいを正している様子だ。
「あれは――」
明日が、立ち止まって警官の注意を引いた。
繁華街を通りがかったところで、騒ぎに気づいたのだ。
「ケンカだろうか」
「捕まえて、って言ってる」
明日は走り出していた。初老の市民が逃げていく男の背中を指してわめいている。おそらくスリだ。
「ふむ。行くか?」
「何!?」
警官の眼前で、風間剛志が本性を――天狗の姿をあらわすと、警官は言葉を失う。剛志は構わず、警官を掴んで、空へと舞い上がった!
そして逃げるスリの行く手へ先回り。
放心中の警官をよそに、スリの前へたちはだかると、相手がひるんだすきに追いついた明日が犯人を取り押さえる。その光景に、我に返った警官が、男を鋭く叱責した。
「……」
そんな一幕を、一団のうしろのほうで見守っていたのはオーギュスト・狼だ。
彼は、同行していたはずの柊木新生の姿がいつのまにかないことに気づいている。
明日たちがスリを捕まえた騒ぎのすきに、オーギュストもまた、そっとその場を離れた。
警察を見たいという視察の要望に対して、巡回の誘いを出してきたのだ。警察署から目をそらしたかったのはあきらかである。
案の定、署の付近で柊木新生の背中を見つける。
「なにか面白い発見はあった?」
新生はオーギュストを一瞥して、くわえ煙草の頬をゆるめた。
「警察車両で連れてこられた犯人がいたよ。中に連れていかれるまで『逮捕後の過剰な拘束は不当な暴力だ』と叫んでいた。おそらくだけどノアの警察がおもに取り締まっているのは――」
「政治犯」
新生は頷く。
軍隊は外なる侵略者と戦い、警察は内なる異分子と戦っている。
その正邪は、いまだ世界図書館には判断のしようがなかった。
■士官学校
「ここが、ミラー大佐の言っていた……?」
コレット・ネロたちが訪れたのは、カンダータ軍の士官学校である。
案内の兵士に先導されて廊下を歩く。ときおりすれ違う学生――いや士官候補生は皆礼儀正しかった。
「ここで士官として必要なことをすべて学びます」
廊下側の窓からのぞける教室では、若い候補生たちが熱心に授業を受けているようだった。
「授業を聞きますか? それとも、食堂にでも行きますか」
「ジムはないのか?」
「はい?」
金 晴天が、二の腕に力こぶを作ってみせた。本当は、カンダータにもボディビルダーがいるなら会ってみたかった晴天だが、体を鍛えているものなら軍隊に行けば会えるだろうと、ここへ案内されたのだった。
「トレーニングルームはあります。行ってみますか?」
一応、学内なら、歩きまわってもいいようだ。
「無論、異世界の事も習っているのでござろう?」
雪峰時光は案内役に尋ねた。かれらが異世界についてどのような教育を受けているのか、授業を聞いて確かめてみたかったのだ。
「まさか」
しかし、案内役の兵士は一笑に付すといった反応だった。
「ここで学んでいるのは士官候補生です。異世界方面戦略は軍の重要機密ですから、ごく一部の人間しかその存在さえ知りません」
「そう……でござるか」
あてがはずれた。
なんにせよ、授業がどんなものかは見てみたい。時光は、コレット・ネロに、一緒に授業の見学をしないかと誘うつもりで振り返った。
「……コレット殿?」
着いてきているとばかり思っていた彼女の姿は、そこに見当たらなかった。
一方――、金 晴天は希望通りトレーニングルームに案内してもらっていた。
「やっぱり食い物とかどうしている?普通に食べていると皮下脂肪つきすぎるから、やっぱり卵白のみとか味なしの笹身の茹でたものといった味気ないものばかりかな」
いかにもカラダ自慢といった風の候補生たちが汗を流しているところへ輪に入る。
話してみたかぎり、スポーツ科学については壱番世界と変わらない水準のようである。トレーニングに関しては、サプリメントが支給されている。また、レスリングのような格闘技が盛んらしく、軍隊内にもチームがあって、大会などが開かれているそうだ。
村正ヨーコは、トレーニングルームをざっと検分したあと、授業が行われている教室へ向かった。
教室では先に見学していた紫雲霞月が、作戦の授業なのだと教えてくれる。
「教官も現役の軍人なのだそうだよ」
霞月も教師である。もっとも「魔術学校」の教師であるから、様相はかなり違うが、それでも教えるという行いには興味がある。
この授業はシミュレーション形式で班別に実際に作戦を立ててみるというグループワークが行われていた。
生徒は皆熱心で、優秀だと印象を受ける。軍人の教育機関としては悪くない、とヨーコは思った。
その頃アインスは、最年長の教官を紹介してもらっていた。
「ミラー大佐を知っているか」
「よく覚えている。優秀な男だ」
「どんな生徒だった」
「一言でいえば野心家。しかしそれは必ずしも悪いことじゃない」
「ここを出て最も優秀な成績な者は、現在どの地位にいるんだ?」
「ここはノアの士官学校だよ。当然、将軍たちも皆ここの出身だ」
「昔と今とで、教える内容は変わったか?」
「むろん技術は進歩するが……基本は変わらんねえ」
「そうか」
聞きたいことを聞くと、授業でも見に行くか、と廊下へ出る。――と、アインスはふと足を止めた。廊下の先をよこぎった、金髪の残像を見たのだ。
「コレット!」
コレット・ネロは、名をよばれて、びくりと振り返った。
「どこへ行くんだ」
「……う、うん。ちょっと……」
コレットの様子を見逃すアインスではない。
「なにかあったのか。……独りで何かしようとしたな」
「……。軍隊のことを知りたいから資料を見せてください、って言って、基地の場所を調べたの」
「まさか行くつもりだったのか。そんなことできるわけないだろ。仮にたどりつけたって、忍び込むなんて……独りではムリだ」
「ごめんなさい。でも……私、思うの。ミラー大佐はまだ隠してることがある。たとえば……<世界計>だって持ってるんじゃないか、って。前に聞いたとき、答えるのに間があったもの。どうしてウソをつくの? なにか……なにかあるんじゃないかって……」
「……。そうか。わかった。でも今日は無謀すぎる。機会はまたあるはずだ」
アインスの言葉に、じっとうつむくコレットだ。
そのとき、校舎内の遠くで騒ぐ声が聞こえた。
そしてそれが怒号へ。
それは……勝手に教壇にあがって古生物学の講義をはじめた鵜城木天衣が、つまみ出されたあと、校庭に5メートルもの殻を持つオウムガイの仲間、古生物エンドセラスを召喚して起こした騒ぎであった――。
■教会と孤児院
「あれはなんだろう」
市内を案内されている途上、陸 抗が案内の兵士に訊ねた。
彼が目にとめたのは、星型のシンボルを掲げた、いくぶん周囲と様相の違う建物だった。
「……ああ、教会だね」
「教会。見てみたいな」
「別に面白いものでもないと思うけど」
言いながらも、門をくぐってみる。
礼拝堂らしき建物の内部は、しんとした静謐な空気に満たされている。司祭らしき老人が姿を見せ、一行の姿を見て、おや、と立ち止まった。
そのとき、璃空は窓の外に、子どもの声を聞いた。
のぞいてみると、建物の脇の敷地に芝生が敷かれ、そこで幾人かの子どもたちが駆け回っている。
「あの子どもたちは?」
案内の兵士が、司祭に、説明をしているのに続けて問うてみると、ここは孤児院でもあるのだという返答があった。
子どもたちと遊んであげたり、孤児院でなにか仕事があれば手伝ってもいいかという申し出を、司祭は受け入れてくれた。
「私たちは芸人なんだよ。ほら」
璃空は術符を使って空中に幻の花を咲かせて見せた。
アラム・カーンがサロードで音楽を奏でるなか、ロストナンバーたちが子どもたちと交流する。
イクシスはくまの着ぐるみを着て子どもらと戯れようとしたが、気がひけるのか、最初は建物の陰からそっと様子をうかがっている。そのうち子どもたちに見つかって輪の中にひっぱりこまれ、モック・Q・エレイヴ
が身体をバラバラにしてブロックのように提供しているのを使って一緒に遊ぶようになった。
「この子たちは……やはり戦争で親を亡くした子たちなのかねえ」
朱里・シュリ・コタム・リトが幼い子を膝に乗せ、うしろからそっと抱きながら、ぽつりと言った。
「……」
青梅 要はその様子を、思うところのあるふうで眺めていたが、やがて、
「じゃ、何して遊ぶ?」
と明るい笑顔をつくった。
「結婚式!」
「結婚式ごっこかー、教会だもんね……ってえええ!?」
そこにいたのは、どうやって調達したのか純白のウェディングドレスに身を包んだラミール・フランクールだった。
「こういうこじんまりした教会でひっそりとふたりの幸せを願う身内だけで挙げる式っていうのも素敵よね。さ、いきましょうカナメちゃん、あたしたちのヴァージンロードへ……!」
「バカなコト言わないで!!」
逃げる要。追うラミール。静謐な礼拝堂内に阿鼻叫喚が響いた。
そんな光景が横目に入るが見ないフリをして、陸 抗たちは司祭と話している。
この教会はカンダータで一般に信仰されている一神教の教会だった。信じるものたちが定期的に通ってきて礼拝が行われるという。
「子どもたちは戦災孤児なのかな」
「そうです。あとは、貧困のために親が育てられなくなったりですとか」
「将来は……?」
「働ける歳になれば自立してもらうようにしているのですが……」
と、話を聞いていると、ふいに、陸 抗を持ち上げて連れ去る手がある。
「!? お、おい!」
「ちょっと協力して! だいじょーぶ、アドリブでなんかしてくれればいーから」
「アドリブ……?」
ファニー・フェアリリィだった。
彼女が子どもたちを呼び集める。
「はいはいみんなちゅーもく☆楽しい劇が、はっじまるよお~♪」
「……」
どうやら陸はファニーの人形劇のキャストにされてしまったらしい。
「さ、仲良く並んで下さいまし」
ミルフィ・マーガレットが集まった子どもたちを並ばせており、すでに注目が集まっている。ならばやらねばなるまい……。
飛天 鴉刃が遠巻きにその様子を見て、笑いをこらえているようだった。
話の続きは聞いておいてやるとばかりに、かわって鴉刃が司祭に質問をする。
「こんなことを聞いていいかわからないが、ここには他の宗派もあるのか」
「教えをどう解釈するかによっていろいろな派はありますね」
「……なあ」
壁にもたれてじっと話を聞いていたグレイズ・トッドが口を開いた。
「てめぇはホントに神様って信じてんのか? ガキが親と離れて生きていかなきゃいけねぇとこに神様って奴がいると思ってんのか?」
「……」
神埼玲菜が口をはさむべきか気を使った様子でグレイズと司祭を見比べる。
「構わないのです」
司祭は玲菜に言った。
「神を信じなくとも生きてゆける人はいいのです。私たちは信じることでおのれを律し、それによって生きるしるべにしようとしています。その意味では、実際に神がおられるかどうかは、争っても仕方のないことです」
「……マキーナも神がつくったものと考えるのですよね」
控えめに玲菜が問う。カンダータの災厄の根源となっている存在を神が創造したことを、信仰はどう解決するのか。
「神の意図は問うてはいけません。現にマキーナがいるこの世で、われわれがいかにして生きてゆくかが大事なのです」
玲菜は礼を言って、案内してくれた兵士にも訊ねてみる。
「宗教は形骸化していると聞いてましたけど」
「そうだよ。信じてる人なんてほとんどいないもの。こんなところわざわざ見学したいなんておたくらも変わってるよ」
そんな答えが返ってきた。
日奈香美 有栖が申し出て、食事をつくらせてもらうことになった。
料理のあいだ、綾賀城 流が子どもたちの健康状態を診ていく。
栄養状態は万全ではないようだが、病気の子どもはいないようだ。特に、心配していた精神的な影響もさほど見当たらないので、安堵を見せる流。しかしもっと前線に近い都市では状況も違うのかもしれない。戦地から離れた首都ノアにさえ、戦災孤児がこれだけいるというのだから。
有栖の料理が食卓に並んだ。
豪華な献立に歓声があがる。
「みんな幸せになれるといいなぁー」
シャチが、食べている子どもたちを見て、ふと呟いた。それは多くが同じ思いだったろう。シャチの瞳は、なにかを思い出すようにどこか遠い。
「将来は、何になりたいのじゃ?」
黒藤虚月が訊ねると、「先生」とか「お医者さん」とかいう声が返ってきた。
日が暮れるまで、ロストナンバーたちは孤児院であたたかなひとときを過ごしたようだ。
■劇場と歓楽街
地下都市では、照明の光量を変えることで、昼夜を知らせているらしい。
ノア市はうっすらと薄暮に覆われる頃、三ツ屋 緑郎たちはネオンが輝く繁華街を歩いていた。
緑郎が劇場を見てみたい、と言ったのでここへ案内された。
「おっと、そっちは……」
案内の兵士が緑郎の年齢を考えてか、最初に立った劇場の前から彼を引き離した。振り返ると、引き離された看板には、きわどい衣裳を着た女性のポスターが貼られていた。大人向けのショーのようだ。
かわりに、いくぶん上品そうな劇場では、ショーやミュージカルが演じられている。
演目を確かめているあいだ、間下 譲二がそっと集団を離れたことに気づいたものがいただろうか?
このあたりは混雑しているので、そこにまぎれこむのは容易だった。大通りを外れると、予想どおり、いかにもな空気がただよっている――。
間下譲二がやってきたのは、劇場街の裏手の通りだ。
表通りの華やかさから一転、このあたりは薄汚れた風体の男たちが集まっていていかにも治安が悪そうである。
「よぉ」
譲二はたたずんでいる一人の男に話しかける。
蛇の道はヘビなどというが、譲二のカンで、コイツは口入れ屋のようなものではないかと検討をつけたのだ。
「なんか景気のいい話はないもんかね」
「……なんだおまえ」
「ちょっとよそから来たんだ。……なんか飲むかい」
真似マネーでつくったカンダータの紙幣を慣れた様子で握らせると、相手も含んだようだった。
「そうだな……よそってどこだ」
「そいつはちょっとな」
「荷物を運ぶ仕事ならあるぜ」
「儲かるのか」
「バレないようにたくさん運べりゃあな」
よくよく聞けば、要するに違法に他の地下都市に物資を輸送――いや、密輸というべきか――をするということのようだ。ブラックマーケットのようなものがあるのだろう。譲二の頭に、こういうときだけ天才的にひらめくものがあった。カンダータの地下都市は地下鉄で結ばれている。……ロストレイルだ! どうにかしてロストレイルを走らせることができれば大量の闇物資を運べるではないか。ロストナンバーが視察のために市内に散っている今がチャンスだ。なに、ロストレイルのスピードならすこし出発が遅れたところで……
「こんなところで奇遇ですね。道にでも迷いましたか」
「っ!?」
凄まじいスピードで皮算用していた譲二の肩に手を置いたのはニフェアリアスだった。
「間下譲二さんでしたっけ。さあ、行きましょう。みなが心配するといけませんから……ね!」
華奢なニフェアリアスだが、うっすらと浮かべた笑みのなかで、眼鏡の奥の瞳だけは笑っておらず、その眼光があやしい赤い光となった瞬間、譲二はもう裏通りから連れだされていた。
最初から、譲二に気づいてあとをつけてきていたらしい……。
「何これー! すっごいキラキラしてるー! パティなんだかわくわくするー!!」
「ちょっと、あんまり離れないで、はぐれるよ」
パティ・セラフィナクルがふらふらと劇場に近づいていくのを、案内の兵士が呼び止める。
その劇場はずいぶん人気の劇場のようで、大勢の観客がエントランスから吸い込まれていく。
「これは? ええと」
「ビクトル・ランス曹長」
「ビクトルさん」
三ツ屋 緑郎がつとめて相手の名を呼んだ。
「ここは歌姫ナターシャのステージだ。予約がないととても見れない」
「人気がある人なの?」
きらびやかな衣装を着た若い女性が、ポスターの中で笑っている。
「ナターシャはカンダータ1の歌手だろう!」
「へえ、見たかったなあ、残念」
「立ち見なら入れるかもしれない。聞いてくるからここを動かないで」
そういってランス曹長は劇場へ走った。
「……あれは自分も見たいのだ」
ぼそりと、魔王が口にする。
「『面倒な仕事』だと思っておる。『せめてこういう役得もないと』とな」
「心を読んだの?」
魔王は頷いた。
「俺はこっちのほうが興味あるな。さっき人ごみで渡されたんだが……」
響 慎二がそう言ってチラシを見せた。『鉄と血』と題された、小劇場の芝居のようだった。
曹長が戻ってくるまえに、慎二はそっと場を離れる。
結局――。ランス曹長は軍の威光を使ったらしく、二階席の端でステージを見ることができた。歌姫ナターシャは容姿も可憐で美しいが、なによりその歌声は素晴らしいもので、緑郎も感心しきりだったし、パティは華やかなステージに見入り、気がつけばなぜか魔王も感動して号泣していた。
一方、慎二が向かった小劇場では、演劇というにはあまりに荒削りな、舞台のかたちを借りた現体制への批判が演じられており、「世相を知るには観劇が一番」というのは間違いなかった、と頷くことになるのだった。
「こういう場所があるって事は、まだ心に余裕があるって事だよね。良い悪いは別にして、余裕がないと生きてくのも辛いもんね。マキーナなんてのも地上に出るんだし」
と、ロナルド・バロウズ。
「まったくです」
隣で応じたのはニフェアリアスで、そのまた隣では間下譲二がふてくされた様子で水割りを舐めていた。
そこは劇場街の一画のバーであり、ジャズに似た音楽が低く流れている。
やたら胸のあいたドレスの女性の歌手が店の簡易なステージで歌をうたっていた。
「どっちが可愛いと思う?」
ロナルドが訊いた。
「どっち?」
ニフェアリアスが視線を巡らせると、もう一人の女性というのは、テーブル席で客を集めている金髪の女――ベルダだった。ベルダは地元の男たちを相手にカードゲームをしているらしい。カジノディーラーの彼女に素人がかなうはずもなく、男たちはすっかり巻き上げられたが、ベルダはその金で店中の客に一杯おごってやったそうである。
*
ぱたり――、とレポートを閉じて、ミラー大佐は息をついた。
「報告ご苦労。大きな問題がなくてさいわいだった」
「士官学校での騒ぎも不問に?」
「もちろん。これしきのことをわざわざ問題にしていったいカンダータに何のメリットがあるのかね。ああ、一応、将軍の耳には入らないようにもみ消しておくように」
「了解致しました」
「ランザーグ市のクレイン隊の報告はどう思うね」
別の声がかかった。
「あちらについても予想通り。すべて予定どおりに進めて問題ないだろうね」
ククク、と喉で笑った。
「世界図書館は世界に介入するのをよしとしないそうだが――。そうではないのだ。世界図書館ではなく、世界図書館を使って私が変えるのだよ、この世界を。この私がね」
![]()









