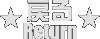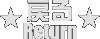|
<ノベル>
「…………うそ」
ダイノランドが出現した頃、星砂海岸に流れ着いた卵から誕生したちいさな怪獣を、ぎっしーと名付けたのは流鏑馬明日である。柊邸の庭の池で飼われているぎっしーと再会を果たした明日は、それが首を伸ばせば明日の身長を越えるほどに成長しているのに立ち尽くすよりなかった。
ざぶん、と怪獣が池に潜る(怪獣が池の容積の半分以上を占めている)と、水しぶきが高くあがって、雨のように明日の上に降り注いだ。
「おーい、なにしてんだ、そんなところに突っ立って。お、雨か?」
「……」
「晴れてるから狐の嫁入りか? ……さあ、坐ろうぜ」
桑島平にともなわれて、テーブルへ。
円卓の中央には、見事な薔薇が飾られていた。
「どうかな?」
「きれーーーい」
リオネが瞳を輝かせる。
花を用意したのはクラスメイトPだ。
「リオネちゃん、お茶の準備はOKだよ」
「ありがとう。……ええと……、おあつまりいただき、ありがとうございます」
誰かに教えてもらったらしい言い回しで、リオネは挨拶をすると、スカートの裾をつまみあげて、ちょっと腰を落として例をした。
ある晴れた日の昼下がり――、柊邸の庭でのお茶会が始まった。
★ ★ ★
「お菓子の数は大丈夫、と――。あ、紅茶はお湯を入れたあと、この砂時計をひっくりかえしてくださいね。砂が落ち切ったら飲み頃だって伝えてあげてください」
小日向悟が、厨房でホテルスタッフのワザを発揮していた。
「はい、かしこまりました」
銀盆の上にカップとソーサーを並べ、メイド服の二階堂美樹は優雅に微笑む。
普段は白衣で研究室を闊歩する美樹だが、ここへ来てメイド服を着たとたん、何かのスイッチが入ってしまった。
今のわたしはお屋敷にお仕えするメイド!
少なくとも彼女の意識の中では、優雅なきらめきを身にまとい、背筋を伸ばして給仕につく。
美樹をはじめ、手伝いにきてくれた面々を、もとからいる家政婦たちが微笑ましげに見守っていた。
「みなさんは、もう長く……?」
大柄な身体にひよこエプロン姿のランドルフ・トラウトが、家政婦に話を聞く。初老の女性は、もう何年も、柊邸に通っていると教えてくれた。それはあるじが市長になる前で、もちろん、魔法がかかる前からのことだ。
「最近は……街が騒がしいでしょう」
おずおずと、ランドルフは訊ねる。
そうねえ、と女性は笑った。
「でも私は他の町を知らないし、ここが好きだから。柊さんも、よそに移るわけにもいかれないでしょうしねぇ」
「はあ、それは……市長さんですものね」
「……もっと静かなところのほうが――と思われることもあるみたいだけど……」
「おっしゃー! 今日は飲むぞーっ! 紅茶だけど、飲む! がばがば飲んでやる!」
桑島が高らかに宣言する。
「もう、桑島さん」
明日が、恥ずかしそうに袖を引くが、彼のテンションは下がらなかった。
「飲まずにやってられるかって、これから……大仕事なんだしな」
「……」
桑島はネガティヴゾーンの探索部隊に参加することが決まっている。
「……まあ、多少のリスクはともなうとはいえ、事態が好転すればいいのだが」
桑島の言を聞き、言外の意を汲んで、シャノン・ヴォルムスが呟いた。
あの不可思議な異世界への探索に、危険がないはずはない。
だがそれが必要なことであると、多くの市民が考えているからこそ、行われることになった探索なのだ。
今日のシャノンは正装だった。傍らではお揃いのスーツに、ネクタイだけがリボンタイになっているルウが、出されたケーキを熱心に食べていた。
その髪をやさしくなで、シャノンは、頬についたクリームをとってやる。
「ほら、もたもたしてるから、もう始まってしもてるやないの」
花咲杏が唇を尖らせた。
「あそこの席が空いておるぞ」
ゆきが空席を指す。
杏とゆきが両腕にしがみつき、ひきずるようにして連れてきたのは狩納京平だった。
「ったく、嬢ちゃんたちにゃあかなわねぇぜ」
苦笑しつつ、テーブルにつく。
ティースタンドに並んだケーキやスコーンを見ると、まんざらでもない気分になってくる。
まあ、いいか、たまにはこういうのも。
そんなことを思いつつ、出された紅茶を一口飲むと、ぴょこん、と音を立てて頭の上に花が咲いた。
「……ん」
ファーマ・シストが、せめて場をなごませようと用意したお茶の効能であるらしかった。
「これは、『すこーん』と言うのか。して、これをつけて食べればいいのだな? なに、『くろすてっど……くりいむ』――難しい名前だな」
岡田剣之進はお菓子の名前を逐一、隣にかけた成瀬沙紀に訊ねている。
リオネも6歳の子どもとはいえ、女性には違いないのであって、女性に招待を受けたからには万難排して駆けつけねば、と勢い込んでやってきた剣之進である。武士の正装である裃で登場しているところに気合いの入れ具合があらわれていた。
隣に座った沙紀も、7歳の、小学生だったが、やはり女性には違いなく、剣之進はせいいっぱい、同じテーブルのものたちにも楽しい時間を過ごしてもらおうとするのだった。
一方、当の沙紀は、いつもよりおしゃれな服を着て、お茶とお菓子は美味しいけれども、そろそろ別のテーブルに移りたいと思っていた。隣の「時代劇のひと」はまあまあ面白いけれど(顔的な意味で)、沙紀としては、アニメに出てくる魔法使いのスターと話がしたい。
視線を遠くに投げれば、リオネが、たくさんの人に囲まれているのが目に映る。
その様子が、なんだか、うらやましく思えて――。
「沙紀殿」
ふいに、剣之進が、テーブルの上のナプキンを手にとった。
なにやらむにゃむにゃいって、ぱっとそれをひるがえせば、色とりどりの花束が!
「!」
すごい、「時代劇のひと」も魔法を使えた!
瞳を輝かせる沙紀。
その肩越しに、各テーブルにマジックグッズを仕込んでいてくれた悟が、剣之進に親指を立ててみせる。
★ ★ ★
リオネの足元では、二匹の犬がじゃれ合っていた。
一匹は、先日、リオネが引き取ることになり、『いりす』と名付けた犬。そしてもう一匹は、アレグラが引き取った『ヴィベルチェ』だ。
「地球人、見ろ、コイヌ、大きくなった。凄い元気」
自慢げに語るアレグラ。リオネは彼女が言うところの「地球人」とはちょっと違うが、リオネはにこにこと犬たちの様子を見ていた。
「いつも楽しいぞ。楽しい、嬉しいだから、お前、今度遊びに来い!」
アレグラは言った。
リオネがどういう存在であるか、よく理解しておらず(正確には聞いたが忘れてしまった)、とりあえず、お茶に呼んでもらったから今度は家に誘えばいいと思っているようだった。
「リオネちゃんって、普段はどうしてるの?」
有栖川三國が、リオネに訊ねた。
「どうって?」
「ええと……この市長さんのお家にいる時は、何してるのかな、とか」
見た目は普通の6歳児。その実、神の娘だという彼女が、どのような日常を送っているのか、三國は興味があったらしい。
「んーとね。ぎっしーやいりすと遊んでるかな? 宿題もちゃんとしてるよー。あと、みだすが汚れてきたら拭いてあげるの」
その様子を思い浮かべて、人々の間に微妙な笑いが広がった。
「リオネちゃんは、夢はある?」
と、三月薺。
「ゆめ?」
「うん、将来、何になりたいとか」
「パパみたいなお仕事をすると思う。薺ちゃんは?」
「私は……。今は、みんなとの楽しい毎日が続くといいかな」
「それはりおねもいっしょだよ」
「……リオネ、おうちに帰りたい?」
ティースタンドの上に、ちょこんと腰かけていたリャナが、そんなことを言った。
リオネはちょっと首を傾げる。
「そう思うときもあるけど……りおねは、ぎんまくしが、すき」
「ね――、リオネちゃん」
明日が、いくぶん真剣な面持ちで言う。
「もし……あなたが神のもとに帰る時。銀幕市の皆の意見を聞いてほしい。突然にやってきて、突然去っていくのはやめてほしいの」
「……」
リオネは一瞬、驚いたような顔をしてみせた。
そして、すこし顔を曇らせる。
「……リオネちゃん?」
「それは、りおねにはきめられないの」
神の娘は言った。
「今、りおねは、神さまだけど、神さまじゃないから。……でも、いつか、許してもらえるんだったら」
「リオネちゃん」
「わ!」
肩越しに、大きな、ピンク色のふかふかの毛皮のくまが顔を出して、丸い瞳でリオネを見つめていた。
「あなたの『いつか』は必ず来るわ」
くまのぬいぐるみをよけると、夜乃日黄泉の姿があった。
「とってもがんばってるもの。私も、協力は惜しまないつもり。いろいろ考えて、このお茶会だって、リオネちゃんが自分で考えたことのひとつでしょ?」
「うん……」
「君は間違ってない」
続歌沙音が、リオネにお茶のおかわりを注いでやりながら、言った。
「自分の出来ることを探して、出来るだけやって、誰かのために何かしようとすることは、何も間違ってはないと思うよ。……それでも納得できないなら、納得できるまで考えるのもいいけれど」
でも思いつめるのはよくないけどね、と肩をすくめる。
七海遥も、同意をあらわして、力強く頷いてみせた。
「全部上手くいくとは限らないけど、何をするのでも、自分は精一杯やったんだって思え
るような事をするのが一番なんじゃないかな……? 許すとか許されないとか、そういう
難しい事は解らないけど……リオネちゃんが銀幕市のこと大好きだって思っててくれたな
ら、私は、それだけで十分なんじゃないかなって思うよ。リオネちゃんの、みんなのために頑張ろうっていう気持ち、銀幕市のみんなにも神様にも、絶対、伝わってるはずだもん」
「そう――かな」
「どうして、『これでのいいのかな?』って、思うの。なにが、ひっかかってるのかな」
吾妻宗主の言葉と優しい声音は、すこしでも、リオネを理解したいという思いにあふれたものだった。
「『ばつ』がないといけないから。……セーラちゃんがいったみたいに、今、りおねがここにいるのは、りおねの『ばつ』なんだもん。でもね……りおね、ここにいることが、とっても嬉しいの。みんなといるのがとっても楽しい。でも、『ばつ』がないと、許してもらえないでしょう?」
「リオネは、許してほしくて行動してるの?」
太助がぼりぼりとビスケットを食べながら、言った。
「許す許されるってのは、とても難しいものだから、そんな簡単にはいかないよ。……『ばつ』っていうか……ぜんぶ、勉強なんじゃないかな。神様って、何でも知ってて、全部のことを見てるものじゃん? 上手くいってもだめでも、結果をぜんぶ受け止めるのが神様の勉強だと思うね、俺は」
なにやら含蓄のある言葉が狸から出てきたので、おお、と場にかすかなどよめきがあった。
しばし、他に発言するものはなく、狸がいいこと言った!的な空気が気恥ずかしかったのか、わざと大声でお菓子のおかりを注文する太助であった。
「あなたは、許されたいのね?」
太助の問いを繰り返したのは、Soraだった。
澄んだ茶色の瞳が、リオネをじっと見つめる。
「…………本当は、よくわからない。りおねが許してもらえるってことは……、だって……」
「終わり」
はっ、と誰もがその言葉に息を呑んだ。
あえて舌のうえに上せると、ほろ苦く溶けてゆく言葉だった。
「あらゆるものに終わりがあり、その終わり方にこそ意義があります。リオネ様、あなたはどのような<終わり>を望まれるのでしょうか?」
白姫は、躊躇なくその問いを発した。
「……みんなが、もう、かなしいめにあわなければいいと思う……」
ちいさな声で、神の娘は言った。
「ありがとな、リオネ」
シュウ・アルガが、彼女の銀の髪をなでる。
「俺はさ、今、そうやって、リオネが、みんなの役に立とうとして、俺たちのしあわせを考えてくれるってことが、すごく大事だと思うぜ。前も言ったけど、俺はリオネに感謝してんだ。他にも、同じように思ってるやつ、いるんじゃないかな」
そう言って、同意を求めるようにベアトリクス・ヴェルンガルドを見遣ったが、彼女は、なぜだかちょっとムッとしたふうで、そっぽを向いてしまった。
ただ、「余もそちは頑張ってると思うぞ」と、付けくわえつつ。
「のう……、りおね。忘れないでほしいんじゃよ。おぬしがしたことを恨みに思うものもいよう。じゃけど、おぬしに感謝しておるものもおるからの。そのどちらのことも、忘れないでおいてほしいんじゃよ」
ゆきが、訥々と語る。
そして、ずっとただ黙って話を聞いているばかりだった西村が、次いで、ようやく口を開いた。
「私……は、映画の中に、大切な……人が、いる。だから――悲しくない、と言えば……嘘に……なる……。だけど……私――は、この街が……好き。この街の……人たちが……好き。この街へ連れてきてくれた……あなたが、好き」
「急にこんな平和ボケしたところに実体化させられて、困ったもんだナ!」
大声で言ったのはクライシスだ。
「ま、ありとあらゆるピンチを乗り越えてきた俺にはこのくらい……たまにはこういうのも悪くないっていう程度だけどナ!」
多少、遠慮のない発言があったとしても――、少なくとも、この場で、面と向かって悪意をあらわすものは誰もいなかった。
安堵したような、照れたような表情で、リオネは、微笑む。
たとえそこに、いくぶんか陰りを含んでいたとしても、彼女は微笑んだのだ。
鬼灯柘榴はそんな様子を遠目に眺めながら、やがて視線を、つい、と別の方向へ投げた――。
★ ★ ★
「陽の光のもとで開かれるお茶会は実にすばらしい、そう思わないかい? ボクは実に愉しい。さあ、これは余興さ、よかったらどうかな?」
ジャック=オー・ロビンが刃物に変えた指先で、紙ナプキンを人型に切り抜いた。
それはぱたぱたと開くと、何人もの人型が手をつないだ連なりになる。
綾賀城洸は素直な驚きを見せて、その作品を、カメラに収める。
同じく、お茶会を楽しむ人々の様子に、一声かけてはシャッターを切る。
カシャリ、カシャリ。
カメラの音がするたびに、笑顔の記録が増えていく。
柊市長が、執務の合間をぬって顔出しにあらわれた。
市長と間近に話をする機会などそうそうないから、彼の周囲にも、市長と話したいというものたちが集まってくる。
「われわれムービースターを市民として受け入れてくれたことに、心から感謝するよ。何か困ったことがあれば、いつでも呼んで欲しい。私は、君たちの力になりたいんだ」
柊木芳隆がそう述べると、あまりに率直な物言いに恐縮したような様子の市長だ。
「ところで、貴方はなぜ、リオネの面倒を? 他に預けられるところはたくさんあっただろうに、多忙な市長自ら、自宅に住まわせるなんて」
ルークレイル・ブラックがそんな疑問を口にした。
話しながら傾けるカップの中身は、ブランデーを落とした紅茶――というより、紅茶を落としたブランデー。深みのある洋酒の香りが漂う。
「リオネは……神の娘だというけれど普通の子どもに見えましたし……放っておけなかったんですよ。……この家は、独りで住むには広すぎますしね」
と、言ってから、とらえようによっては嫌味に聞こえると気づいたのか、市長は、あわてて言い繕った。
「あの、そういう意味ではなくて、独りで住むと寂しいってことですよ。この家も――そのほうが喜ぶと思いますから」
そんな市長の様子に、くすり、と笑みをもらし、針上小瑠璃が口を開いた。
「市長は、リオネの事、どお思ぉてはるん? この夢が消えても、リオネに居(お)って欲しいんか……」
「それは、リオネが望むようにしてやれればと思います」
「……そうそう、あたしら、何も出来ん一般人は、魔法が効かん区域、作ってもろたら……思うてるんです」
ふいに、小瑠璃が話題を変えた。
「ああ、それは……みなさんにはご迷惑を……」
ムービーハザード自体の責任は市長にはないわけだが、こういう局面では謝ってしまうのであるらしい。
リオネの魔法が効果を発揮していない場所は銀幕市のどこにもない。
そればかりは、魔法によって生み出されたムービースターにもどうすることもできないことであったから、市長としてもただ謝るよりないようであった。
★ ★ ★
さて、庭ではなごやかなお茶会のひとときが続いているその頃。
柊邸の廊下を歩む3つの人影があった。
「ナンチャッテ家庭訪問だネ!」
先頭を行くのはクレイジー・ティーチャー。そしてそのあとにレモンと浅間縁が続く。
「ここはなにかナ〜?」
3人が忍び込んだ部屋には、驚くほど大きな液晶のテレビが置かれていた。
そしてずらりと並んだDVD。
「おお〜、さすが市長。なかなかレアなグッズも揃えてるじゃない」
『スターフォウル』の限定DVDBOXを見つけて、縁が声をあげた。
「あら、これはSAYURIの映画だわ! 市長もあんなわかりやすい色香に惑わされるなんてまだまだね」
言いながら、持参していた自分のDVDとすり替えようとするレモン。
それもパッケージはそのまま、ディスクの中身だけを交換している。悪質だ。
「……アレー?」
クレイジー・ティーチャーが、部屋の窓を指した。
そこから見える庭を横切る黒い人影を、3人は見た。
「あら。ウォンじゃない? 彼、来てたっけ?」
「私は見なかったけど……」
縁は首を傾げた。
3人は、そろりと窓辺に近づき、カーテンの影から頭を並べて庭を除いた。
庭といっても、テーブルを並べた会場ではなくて、建物の陰になった、敷地の裏手である。
かれらはそこに、ユージン・ウォンと――黄金のミダスの姿を見る。
「『自主映画製作サービス』の一件は知っているな」
低い声で、ウォンは言った。
「あのアズマ研究所でさえ、人為的にムービースターを実体化させる技術は実現できていない。そして、角のあるバッキー……」
生ける彫像は、いにしえの賢王をかたどった顔を、ウォンへと向けた。
『我も気にはかかっている。最初はそれも歪みのあらわれのひとつかと考えていた。しかし……』
「この街の、危うい天秤を傾けようとしている輩がいることは、間違いないだろう」
『……。何ゆえだ。そのようなことをして得をするものが――』
言いかけて、ミダスは口をつぐんだ。
と、いっても、声に出して喋っているのとはすこし違うので、そういう表現が許されるならば、だったが。
『まさか……』
ミダスの「声」に、あきらかな狼狽が浮かんだ。
★ ★ ★
「みんな、ありがとうね」
リオネは言った。
クラスメイトPが、花冠をつくって、リオネの頭上にそれを乗せてやる。
はにかんだような、笑みを浮かべる。
やわらかな紅茶の香りの中に、リオネと、銀幕市民たちの、笑い声が溶け込んでいった。
★ ★ ★
その様子を――
いずことも知れぬ場所で、水鏡に映し、眺める一対の目がある。
「そうだ、リオネ。それでいい」
オネイロスは満足げに頷いた。
そして、その唇を引き締める。
「…………しかし、ミダスよ。そのようなことがありうると思うか」
その問いに対するいらえは、傍らの台座に飾られた花瓶の中の、黒い薔薇から聞こえてきた。
『かのものたちが放逐されたまさにその時から今まで、一度もなかったことかと』
「リオネの魔法のせいか?」
『歪みは思いのほか大きく、あのような力の溜まり場まで創る有様。それが世界の壁にほころびをつくったところで、驚くにはあたりますまい』
「……。リオネの罰が成就するのはそう遠くない未来であろう。それをさらなる災いの呼び水にしてはならぬ」
夢の神は、地上を映す水面へ、すっと腕を差し伸べる。
「慎重にゆかねばな。神の手による介入はできぬ。さりとて、狡猾な彼奴らの尾を掴むには……」
神の掌のうえに銀色の光が灯った。
そしてそれはゆっくりと、地上へと下ってゆくのだった。
|