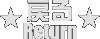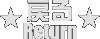|
<ノベル>
黄金のミダスが指し示す先で――。
志願した勇士たちが、次々に『穴』へ身を投じてゆく。
その身体は万有引力の法則にとらわれることなく、ミダスの魔力によって、ゆっくりと降下していくのだった。
まず、突入援護の先遣隊が行く。
それから8つにチーム分けされた探索部隊。
「ボクも行きたい行きたい行ーきーたーいー!!」
クレイジー・ティーチャーが喚いているのは、探索部隊に志願したがいろいろな事情でその中に加われなかったかららしい。
「何サ何サ、クレイジー先生の知的好奇心をナメちゃダメだヨ!? こーなったらコッソリヒッソリ突入してやろうじゃないカァ!!」
などといいつつ、鼻息荒く突進するが、じたばたと四肢が空を掻くばかりでちっとも前に進まないのは、その白衣の裾を、浅間縁がしっかりと踏みつけているからだった。
「本当は私も行こうと思ってたんだけどね」
縁は、ぽつりと言った。
けれど周囲の心配が彼女を踏みとどまらせた。
今のこの空気は――あの時に似ている、と縁は思う。
空から、死の兵団が舞い降りてきたあの時と。
まさにミダスはきっと、あのときもああやって兵士たちを降下させていたはずなのだ。
すなわちそれは、人の心を騒がせずにはおかない戦場の空気。
探索活動といいながら、それでは、これは戦争だというのか。
ベースキャンプで行われている炊き出しを手伝うべく、縁は踵を返した(ぱっと足を話すと前のめりにクレイジー・ティーチャーが地面にスライディングしていった)。
駆け出して――ふと、立ち止まる。
そしてもういちど、『穴』のほうを振り返った。
「誰も傷つかずに終わらせられたらいいんだけど。…………あの『女の子』も」
★ ★ ★
宙に浮かぶ氷が、光を反射し、照明の役を果たしてくれる。
それはレドメネランテ・スノウィスの能力だ。
「みんな。無事に戻ってきてね。ボクも、此処でだけど、一緒に闘うから」
彼の思いは、他の多くのものも同じだったろう。
まず、いくつもの横穴へ、先遣隊が様子を見に行く。
「!」
『穴』の底に響くはばたき――
「ここに! 敵が!」
ユーフォリア・ノクスィトゥルヴェルが声を張り上げた。
深海魚を思わせるフォルムの異形の存在――ディスペアーが、彼女に組みついていた。
ひゅん、と空を切って飛来したナイフが、その胴体に突き刺さる。リカ・ヴォリンスカヤの投げたナイフだ。
「……」
攻撃が命中したのだというのに、なにか汚いものを手でさわってしまったように、リカはたじろいだ様子を見せた。周囲からどう見えていたかは知らないが、本当はこんなところに来たくはない。あの彼が探索部隊に加わっていなければ、支援活動にも参加しなかったろう。朱鷺丸が、鉄パイプでディスペアーにとどめを刺しているのを、おそろしげに眺めた。
「こっちにもいるぞ!」
誰かが叫んだ。他の横穴の中にも、なにものかがうごめく気配がする。
無言で、そこへ飛び込んで行ったのは昇太郎だった。
南雲新が、その後を追う。いつもの二刀流の片方はディレクターズカッターに変え、余ったひとつは先を行く昇太郎に貸している。
飛び込んだ横穴の中には、ディスペアーたちの一群がいた。
昇太郎はすでに取り囲まれているが、まさに寄らば斬るぞの勢いで昇太郎は刃を振るう。血なのか何なのかわからない、闇が凝固したような体液がしぶく。
新もそこへ斬り込んでゆく。
先遣隊も8方向へ分かれてそれぞれが横穴へ。その中には、レディMが見つけたようなごく狭い穴もあれば、かなり広めのものもあり、さまざまだった。そしてディスペアーの姿が見られたものもあれば、拍子抜けするほどあっさりとその先へ抜けられたものもある。
あるいは、横穴では何にも遭遇しなかったが、その先で、敵影の発見に至った場合もあった。
「なんと……」
古森凛は、言葉をなくした。
広がる空と海は、シュールレアリスムの絵画のように、どこか現実離れしていて、そこに果てしのない不安と狂気の色彩をはらんでいるようだった。
凛は、その身にそなわる悟りの力を、ゴールデングローブの作用をさらに越えて、自身でも抑えこまねばならなかった。
この世界には、悪意しかない。
すべてのものが、彼を拒んでいる。
ぼこり、ぼこり、と、銀幕市からやってきたものにとっては、地面のようにその上を歩くことのできる海原の底から、ディスペアーたちが姿をあらわす。
「ペンギンアターック!」
首輪型のゴールデングローブを装備した王様が、弾丸のように飛び出していく。
それを追って虎の姿のアスラ・ラズワードが背中に弟を乗せて海の上を駆ける。
「子どもとかチビとか関係ねぇ! 俺だって男だぜ! 隅っこでビクビクなんかしてらんねっつの!」
「落ち着いていけよ、ま、気楽にな――」
アスラの背の上からデッキブラシを武器に戦うヤシャ・ラズワードの傍に、ノルン・グラスが沿って、飛びかかってくる敵を受け止めては投げ飛ばしていた。
神龍命も、いつになく真剣な眼差しで、敵へと立ち向かっていく。
「ボクだって……誰かの役に立ちたいんだ……!」
組みついたディスペアーが、かッとあぎとを開ける。そこにずらりと並んだ牙、牙、牙――怯みそうになる心を抑え、全身の力を振り絞って、命は敵を押し返した。
……と、ふいに軽くなったのは、電撃のように飛びこんできて、敵を蹴り飛ばした影があったからだ。
「世界が、悪夢で終わるはさせません」
黒龍花の凛々しい横顔が、笑みを浮かべる。その腕に光る腕輪型のゴールデングローブ。ムービースターはその装置の作用で能力を制限されるが、身体能力を生かして戦うタイプはかなり力を残していられるようだった。
ごう、と炎が舞った。
柏木ミイラが、缶スプレーとライターで即席の火炎放射を行ったのだ。
その火炎がつくった一瞬の隙をとらえて、ティモネが鎌をふるい、敵を仕留める。
「よっしゃ、皆行ってこい!」
今のが見える範囲では最後の一体だったことを確認し、ミイラは横穴から姿をあらわした探索部隊に声をかける。
「危険だと感じたらすぐに帰ってくるのよ。絶対に」
ティモネが真剣な目で告げる。
こうして――、探索部隊各班がそれぞれの担当区域へと送り出されていく。
全体としては、大きなトラブルはなく……少なくとも、探索部隊自体には何の被害も出すことなく、ネガティヴゾーン探索は始められたのである。
あるひとつのポイントでは、ディスペアーの群れを支援班が引きつけている間に、部隊を送りだすという方法がとられた。
風轟が、風の壁をつくりだし、探索部隊を護る通り道をつくったのである。
普段なら難なくできることも、ゴールデングローブをつけた状態ではかなり力がいることを、風轟は感じた。青宵が、他者の力を増幅する力を行使して支援したことで、それは果たすことがかなったのだった。
風轟は、出発する探索部隊に、ゴールデングローブを装着した片腕を、高々と上げてみせる。
輝く黄金は無言のエール。
探索部隊の誰かがそれに応えて手を振ってくれた。
★ ★ ★
すべての探索部隊が出発すると、突入援護の人員と、入口保守の人員の後退が行われた。
探索部隊は無傷で出発したが、そのぶん、盾となった援護班には負傷や疲弊も見られる。
轟さつきのバイクが、『穴』の壁面を垂直に登って爆走してきた。人を抱えている。
「負傷者か! こっちへ頼む。ニグラ、薬草を」
ウィズがベースキャンプを示して声をあげた。効率よく動けるように、キャンプはマルパスのいる本部のほか、救護班、整備班、アズマ研究所のチームなど、役割を分けて設営されていた。設営にあたっては、「海賊船の経営を仕切っているのはこのオレよ」と豪語するウィズの助言の数々が活かされたらしい。
「なるべく使わずに済むことを祈ってたんですけどねぇ」
ニグラ・イェンシッドが、薬草の備蓄を確かめながら、負傷者を救護所へ案内する。
「くそ……なんだあの海……力が出ない……」
「いいから傷を見せて」
ジェイク・ダーナーの負傷の具合を、臥竜理音が確かめた。
ジェイクいわく、いつもの調子で戦おうと思ったがさっぱりだったらしい。彼は魔法や超能力を発揮するムービースターではないが、映画の中では常人離れした怪力を見せる。その「常人離れした」部分がゴールデングローブによって制限されてしまうらしい。
天野屋リシュカが理音を手伝ってジェイクの傷の止血を行った。
他にも怪我人が次々に運ばれてくる。
拠点には一般的な医療器具、医薬品のほか、ニグラの薬草、愛宕が生み出した治癒の力をもつ護符、そしてファーマ・シストの治療薬が揃っていて、かれらを迎えるのだった。
綾賀城洸は、さほどの重傷者がいないことを確認して、まずは安堵の息をつく。
中央病院と連絡をとって、いざというときは病院への搬送の手配をしていたのだ。準備は万端に、しかし、使われないで済むならそれが一番だ。
ベースキャンプでは炊き出しが行われていた。
真船恭一が、戻ってきたばかりの突入援護の班に、おにぎりやスープを薦めている。
「握って、握って、握り固めるべし!」
沢渡ラクシュミがほとんどバレーボール大に匹敵しようかという巨大なおにぎりを作っているのを見て、ハンナが豪快に笑った。
「元気と思いの塊って感じだね。さあ、皆に持っていっておあげ。たくさん食べな? ……それからあんたもね」
ハンナは、恭一自身にも、スープカップを渡した。
「あ、はい……美味しいです」
あたたかなスープが、張りつめた心をなごませてくれる。
「このあたしが作ったんだ、美味いに決まってるだろ、あはは」
「……あれ、ここに置いてあった香辛料知らない?」
槌谷悟郎が、カレー鍋から顔をあげて言った。
「え? ……このへんのは、全部、具にしちゃったけど」
と、ラクシュミ。
「ええっ、じゃあ、おにぎりのどれかに……!?」
はっと、気づいたときには、すでに、このロシアンおにぎりの被害が出て、どこかで悲鳴があがっていた。
だがそれさえも、この空気を和ましてくれるなら歓迎すべき一幕だったかもしれない――、と、豚汁を煮込みながら、モミジは思った。
「大丈夫。あいつらのことだ。無事に帰ってくるべ!」
ゲンロクが、ともに調理に加わっていた続歌沙音に声をかけた。
「え。あ、ああ……」
べつに誰かを心配してたわけじゃ――と、いいかけて、黙った。知らずに、手が止まり、視線が『穴』のほうへ向いていたらしい。
「不安がっている暇があったら手を動かす。できることはいろいろある」
と、ロゼッタ・レモンバーム。
誰もが、目の前の、自分にできることを果たそうとしていた。
「グローブ型っていうのはやっぱり冴えないわよね。それに比べて、どう? あたしがデザインしたこのラブリーエンジェルブレスレットは! まさに優雅とはこのこと! ちょっと聞いてるの?」
レモンが、アクセサリー型のゴールデングローブをチラつかせて自慢しつつ、腰かけている機材の上から、その機材の様子を見ているレオ・ガレジスタに声をかけた。
「聞いてるよ〜。……うーん、ちょっと熱くなってるかな。ここも冷却装置つないだほうがよさそう。真山さん、そこの機械取ってくれますかー」
「これでいいかい?」
真山壱が、機会を運びながら、モニターの前に集まってああでもないこうでもないと言っている白衣の集団――アズマ研究所の面々に目を光らせる。
探索部隊や『穴』の底の待機班から送られてくる情報を分析しているらしいが、今のところ、不審な行いは見当たらなかった。
傍では、萩堂天祢がノートPCとにらめっこしている。その中には、探索部隊をはじめ、今回の活動にかかわった人々の情報が記録されていた。何かの際に、そういうデータが必要になることもあるだろう。
しばらくは――
待つだけの時間が流れた。
サキとディーファ・クァイエルが、折り紙で鶴を折り始めた。
いつのまにか、ふたりに折り紙を分けてもらって、ともに折りはじめるものが増え、皆が一心に、折り鶴を増やしていく。
一羽、また一羽。
ひとつひとつに、探索部隊の無事を願う祈りが、こめられているのだ。
「おんなのこが、しゃしんにうつってた、ってきいたの」
マリエ・ブレンステッドが、傍にいた悠里に話し掛けた。
「え? あ、ああ、そう……そうよ……」
悠里はまさに、ぼんやりとそのことを思い出していたところだったのだ。
前回の調査隊に、彼女は参加していた。あの時、調査隊のひとりの携帯のカメラが、とらえたあの画像は。
「そのこはいま、どこにいるのかしら。ひとりぼっちで、ないているのかしら?」
マリエがなぜそう思ったのかはわからない。
だが悠里は、わけもなく、胸がきゅっと締め付けられるような気持ちになった。
なんだろう、これは。
不安? それとも…………哀しいの?
「お茶でも――入れるね。誰かが持ってきてくれたハーブティーがあったから」
思いを振り払うように立ちあがり、駆けだしたが、そのまま盛大に転んでしまった。
(どうか……)
痛みに耐えて、起き上がりながら、悠里は祈った。
(どうか無事で戻ってきて)
★ ★ ★
「下手な鉄砲でも弾幕にしたら当たるよな、……きっと」
「そうだな。ファングッズはディスペアーにも効くみたいだし」
「でも誤射には気をつけないとな」
「あー、そうかも。味方のムービースターに当たると危ないよな」
白木純一と相原圭の話す声が、穴の底にわんわんと反響する。
とくに圭は、話していないと落ち着かないようで、しきりに、傍にいる誰かに話しかけていた。
「戻ってきたぞー!」
誰かの声に、ふたりははっと声のほうを見た。
「ご無事で!」
十狼が――先ほどまで片山瑠意、理月らと彫像のようにたたずんでいた長身の武人が、帰還した部隊のひとつを迎えていた。
かれらの知人が参加していた組のようで、目に見えて安堵した空気が広がっている。
トトが、二匹の空飛ぶ金魚をしたがえて、にこにことしながら、そのまわりをうろついていた。探索部隊の面々が無事だったことが嬉しいようだ。
それを皮切りに……続々と帰還の報せがもたらされた。
ひとつ、またひとつ。
さいわいにも、大きな怪我をしたものはまだいなかったし、敵に追われて逃げ帰って来たというわけでもないようだ。むろん、ネガティヴゾーン内においては敵に遭遇し、一戦まじえてきたものたちもいた。
いずれにせよ、皆、驚くべき体験をしたようで、興奮してあちらで見聞きしたことをまくしたてるもの、負傷こそないが青白い顔をして黙りこくっているものもいた。
そんな様子を見ながら、RDは、ふん、と鼻を鳴らした。
暴れ回れるかと思っていたが、いまだ出番がなさそうなのである。
このまま、何事もなくすべての部隊が戻ってこれるのではないか――皆がそう思い始めた時だった。
「!」
レイは、門の向こうで、そのどこまでも続くかに見える水平線を眺めていたのだった。
ただ眺めていたわけではなく、すべてのセンサーがあらゆる情報を感知し、収集していた。地上にいるときよりいくぶん感度は鈍い。だがそれでも、肉眼よりは早く、彼はその反応を察知したのである。
「来た。……追われているぞ!」
その声に、一気に場に緊張が走る。
探索部隊のひとつが、こちらへ向かってくるのが見える。そして、かれらを追撃しているディスペアーの群れも。
銃声が、うつろな空に響いた。
走る部隊の最後尾を走るものを、今まさにとらえようとしていた一体が弾かれ、あやしい体液をまき散らしながら海の上を転がった。
柊木芳隆のレミントンM700が続けて火を噴く。
同時に、エンリオウ・イーブンシェンの生み出す氷の弾丸が放たれた。
「んん。おかえり、お疲れ様。あとは任せてねぇ」
場違いなほど穏やかな笑みで、探索部隊を招き入れ、かれらが撤退するのを見届けると、すらりと剣を引き抜いた。
「おまえもとっととこっちへ来い」
銃撃に加わっていたレイの首ねっこをつかんで、ジム・オーランドが彼をひっぱりこむ。
抗議の声を聞き流し、向かってくるディスペアーにぶつかっていく。
RDも、嬉々として飛び出していった。ゴールデングローブがあってさえ、常人に比べればその膂力は怪力の域だ。
この日、保守・撤退支援には数多くの市民たちが参加してきた。
だから、追ってきた群れはすべて、ここで撃退することができたのである。
ディスペアーの異形の死骸はずぶずぶと、海の底へと沈んでいった。
「後は――?」
誰かが訊いた。
まだ戻っていないのは何組か、という意味だ。
「あとひとつだ!」
応えが返ってくる。
そう、それは確か……銀幕ジャーナルの七瀬灯里が同行したチームではなかったか。
「ギャリック! ギャリック! アッチ! アッチ!!」
オウム姿のパイロが、ギャリックの肩の上でぎゃあぎゃあと声をあげた。
「んん?」
ギャリック海賊団を束ねる男は、水平線へと目を細めた。
そして。
「……う――わああ……っ」
声をあげたのはクラスメイトPだった。
「たたた、たいへんだ……!」
そして駆けだしていく。もちろん、状況を知らせるためだ。いつもならここですっ転ぶのが彼のお約束だったが、ゴールデングローブをつけてネガティヴゾーンに立っているといつもの不運に見舞われない。クラスメイトPの声が、探索部隊の速やかな撤退と支援班の増援を叫ぶ。
それは黒い雲のように見えた。
海原の果てにわき起こった黒い入道雲。それが数えきれないほどのディスペアーの群れだと知って、しかし、ギャリックの顔に浮かんだのは、むしろ不敵な笑みであった。
「野郎ども!」
ギャリックが吠えた。
「退路は――俺たちが守るぞォ!」
おう、と威勢のいい声が応えた。
横穴から、続々と、応援がやってくる。
キィン、と弧を描いて飛ぶベルナールの光弾が、カッと閃光をともなう爆発となった。その光に照らされて、こちらへ向けて必死に走ってくる探索部隊の姿がある。
「あと少しです。頑張って……!」
黒瀬一夜が、スチルショットの引き金を引いた。
そのエネルギー弾が命中し、もっとも間近まで迫っていたディスペアーが動きを止めた瞬間、アレグラが手を伸ばして、探索部隊のひとりを掴んだ。そのまま力任せにひっぱりこむ!
「ココを抜けられると、厄介だからなァ!」
続那戯が、歯でピンを引き抜いた手榴弾を投げる。爆発がディスペアーたちを巻き込むのを確認し、槍を手に飛び込んでいく。
那戯の言う通り、ネガティヴゾーンと『穴』とが狭い横穴でのみ通じているここが、もっとも守りやすいポイントだ。この先へ、もしもディスペアーたちの侵入を許せば――あとは『穴』を登った先に銀幕市があるばかり。
「ディスペアーに世界が汚染されたら、銀幕市もあたしたちのいた場所みたいになる? それは嫌。まだ変わる空の色を見ていたい」
ディレッタが変形された腕で近づいてきたディスペアーの一体を叩き落とした。
「あら、アタシだってやる時はやるのよ〜? んふ、ウサちゃんだからって舐めてかかると痛い目見るわよ!」
ニーチェが、アンクレット型のゴールデングローブを装備した脚で見事な蹴りを決める。
「あー、ここ、宜しくない船の底の嫌ーなカンジに似てるわ。人だらけなのに誰も喋んねぇのよね」
シキ・トーダが言うのは、きっと『絶望』のことである。
だが、この状況を予測していたのかどうか、撤退支援に参加した人数は多かった。そして絶望にとらわれているものなど、いない。
鞭をふるい、敵を退けるシキ。その傍らで、エフィッツィオ・メヴィゴワームが、今日ばかりは鉄パイプで敵を叩きのめしている。
「なんでテメェと組まなきゃなんねんだよ!」
こぼしながら、シキが鞭で怯ませた相手の頭らしきところへ、鉄パイプを振り下ろす。
エフィッツィオの銃は、ゴーユンの蛸の足に握られていた。それだけではない、彼女は両の手とすべての足に銃を持ち、そのすべてで敵を銃撃しているのだ。その成果は目覚ましいものがあった。
「ぬお!」
清本橋三が、ディスペアーの一体に突き倒され、身体のバランスを崩した。
「橋三殿!」
飛んできたのは動く甲冑コーターである。
「橋三殿の想い、ウルトラ受け止めた! あとは任せて下され!」
バラッ、と甲冑が崩れたかと思うと、その中にすっぽりと橋三の身体を収納する!
「ま、まて、コーター殿、拙者はまだ死んでは――」
その叫びも、兜の中に呑まれていく。
そんな撤退支援のおかげで、命からがらに逃げてきた探索部隊も逃げ延びることができたようだ。
「あ――っ」
横穴へ飛び込む寸前で、七瀬灯里が躓いた。
危ない、と思った、しかし次の瞬間には、ふわりと漆黒のビロードが広がり、包みこまれたような錯覚とともに、その身が受け止められたのを感じる。
「お怪我はないかな、お嬢さん」
「ブ、ブラックウッドさん」
存外に力強い腕の中で、ごく間近に囁かれたベルベッドボイスに、灯里の心臓が跳ね上がった。
「あ、ありがとうございます……あ、あの――、私、みんなに、伝えなきゃ」
混乱した様子で、だが、おのれの職分を彼女は忘れていない。
手の中のデジタルカメラの、画面に映し出されたものに、ブラックウッドはすっと目を細めた。
「『彼はおののきを知らぬものとして造られている』」
その口から、いにしえの書物の一節が諳んじられる。
『驕り高ぶるもの全てを見下し、誇り高い獣全ての上に君臨している』
★ ★ ★
「なんとか片付いた」
ルイス・キリングが、津田俊介の瞬間移動によって戻ってきた。
最後まで残っていたのがこの二人だ。
あれだけいた敵を、撤退支援の皆ですべて撃退した。
さすがの面々も疲労を隠せないが、同時にやり切った充実感もある。
だがそれは勝利の感覚とは違っていた。
なぜならば、戦いが終わっていないことを、皆、知っていたからだ。
灯里たちが持ち帰ったその画像が、モニターに映し出されると、ベースキャンプ内にどよめきがあがった。
アネモネは思わず、後ずさる。それはひどく、心を乱されるような何かだった。彼の銀の瞳が、すこし、潤んだ。
マルパスは、絶望の海にひそむ巨大な怪物の姿を見据える。
「あれは殲滅すべきだと思う。だがネガティヴゾーン内で戦うことは得策ではない」
敵の力は強大で、探索部隊の持ち帰ったさまざまな報告を聞くまでもなく、ネガティヴゾーンはアウェイに過ぎる。
「ならば方法はひとつしかない。……この銀幕市において、あれと戦い、打ち破るしかないのだ」
マルパスは言い放った。
それはあまりにも危険な賭けだ。
だがそれに賭けよと、時が告げていることを、誰もがはっきりと感じ取っていた。
|